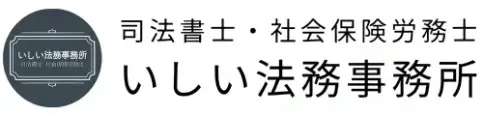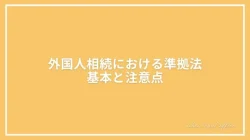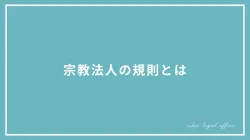累積投票制度とは?取締役選任における少数株主の権利活用
累積投票制度は、少数株主が取締役を選任する際に、その少数株主にも取締役を選出する可能性を与えるための制度です。会社法で定められたこの制度を理解し、適切に活用することで、少数株主の意見を経営に反映させることができます。本記事では、この累積投票制度について解説します。
投稿者プロフィール
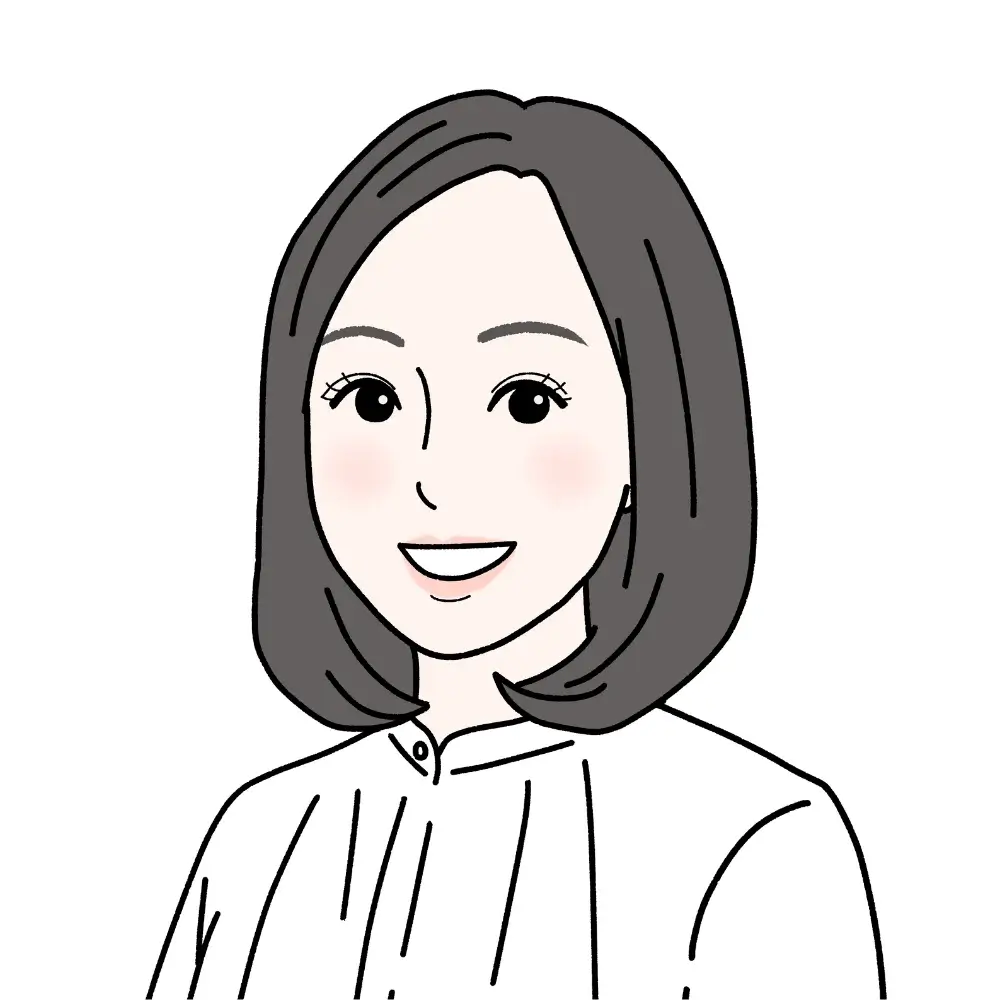
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
累積投票制度とは?基本仕組みと少数株主の活用ポイント
累積投票の定義と仕組み
累積投票制度は、株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)を複数選任する株主総会で利用できる特別な議決方法です(会342条)。この制度では、株主が持つ株式数に、選任する取締役の人数をかけた数がその株主の議決権として与えられます。
たとえば、ある株主が100株を保有し、3名の取締役を選任する場合、100株×3=300議決権を持つことになります。これらの議決権は、特定の取締役候補に集中投票することも、複数の候補に割り振ることも可能です。
累積投票制度を用いた場合、得票数が多い順から当選者が決まります(会342条4項)。この仕組みにより、少数株主でも支持する取締役の選任に影響力を持てるのが特徴です。
通常の選任方法との違い
通常、取締役の選任では、各候補者ごとに賛否を個別に投票し、多数決で決定します。この方法では、議決権の多い株主が複数名の取締役を全員選出しやすくなります。
一方で累積投票制度を使えば、株主は保有株式数に選任人数を乗じた議決権を好きな候補に振り分けることができ、少数株主でも支持したい候補へ議決権を集中投票できます。その結果、従来は反映されにくかった少数株主の声を会社の経営陣構成に反映しやすい制度といえます。
累積投票制度のメリット・デメリット
累積投票制度導入の最大のメリットは、少数株主の意見が経営に反映されやすくなることです。経営の透明性が向上し、健全化につながります。
一方で、デメリットとしては、少数株主の意向が強く反映されすぎることで、経営の一貫性や安定性が損なわれる可能性があることが挙げられます。
累積投票制度を利用するための条件と手続き
定款による排除の有無と注意点
累積投票制度は会社法で株主に認められた権利ですが、定款に累積投票を行わない旨が明記されている場合は、この制度を利用できません(会社法342条1項)。
会社の定款は企業運営の基本ルールであり、累積投票の利用を考える際は、まず定款内容を確認することが重要です。累積投票の排除条項がある場合は、株主総会で特別決議を経て定款を変更しなければ、累積投票制度を利用できません。
累積投票の請求方法
累積投票を実施するには、株主が会社に対して事前に請求する必要があります(会342条1項)。具体的には、株主総会の5日前までに、株式会社に対して累積投票の請求を行うことが求められます。定款に排除規定がない限り、会社は株主からの累積投票請求を拒否することはできません。
累積投票で選任された取締役の解任について
累積投票によって選ばれた取締役も、株主総会の決議で解任することが可能です。
通常、解任の決議は、株主総会の特則付き普通決議によって行われます。しかし、累積投票により選任された取締役を解任するときは、特則付き普通決議では足りず、特別決議が必要となります(会309条2項7号)。
さらに、累積投票で選任された取締役が正当な理由なく解任された場合、その取締役から会社に対し損害賠償を請求される可能性があります(会社法339条)。
まとめ
累積投票制度は、少数株主の権利を守りつつ、経営の多様な意見を反映させるための仕組みです。制度の活用や設計にあたっては、定款や法的要件の確認が不可欠です。
当事務所では、株主総会の運営や会社法務についてもご相談を承っています。累積投票制度・株主総会運営でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。