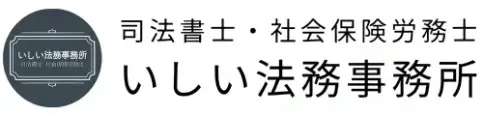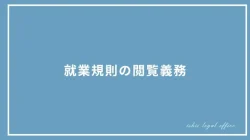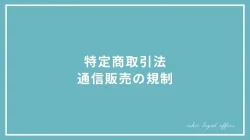消費者契約法をわかりやすく解説
消費者契約法は、消費者と事業者間の情報格差を埋め、消費者の利益の保護を図るための法律です。事業者間の契約や労働契約などは消費者契約法の対象外となりますが、原則としてすべての消費者契約が消費者契約法の対象となります。特定商取引法や割賦販売法など、事業者が守るべき法律はいくつかありますが、消費者契約法はそれらの基本となる土台のような存在です。
この記事では、消費者契約法の基本的な内容ついてわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール
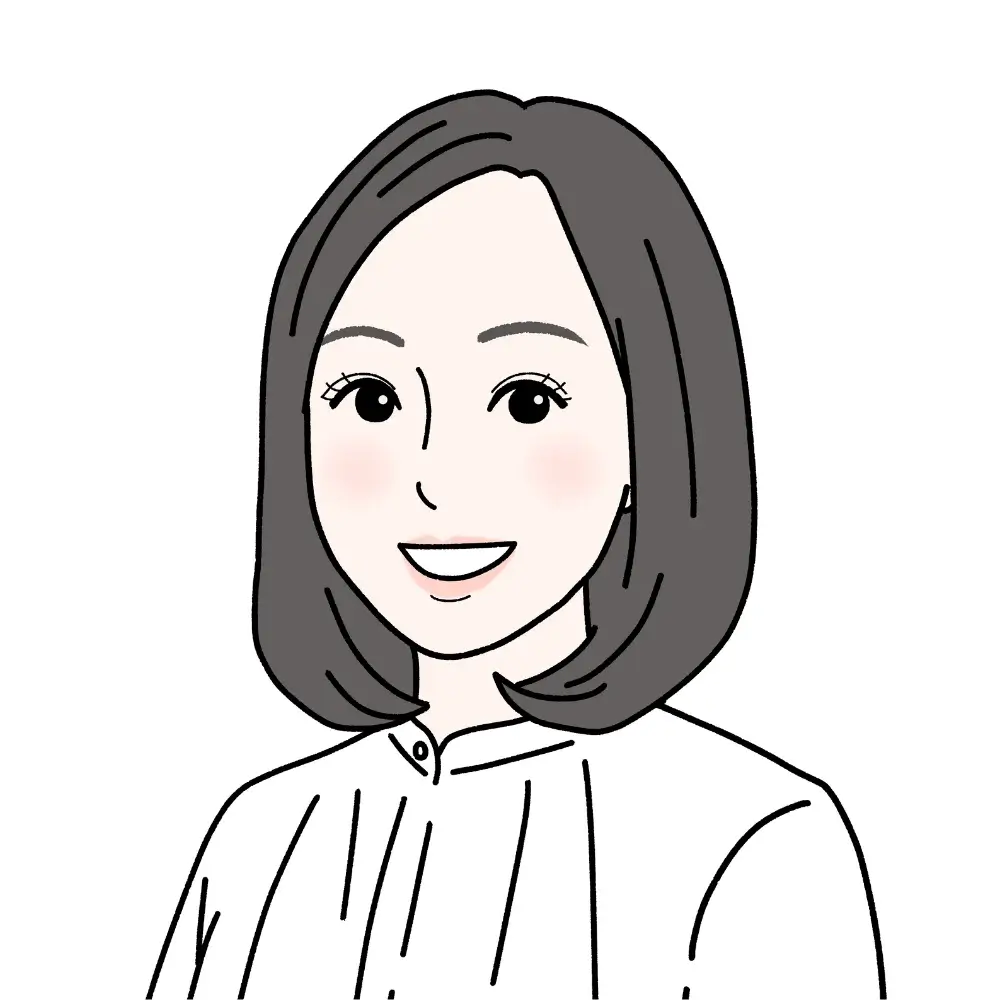
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
消費者契約法とは?基本を理解する|目的と役割
消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれる契約において、消費者の権利を保護し、不当な契約から消費者を守ることを目的としています。
具体的には、事業者が不当な勧誘行為を行った場合や、契約条項が消費者に一方的に不利な場合に、消費者を救済するためのルールを定めています。
消費者契約法は、消費者を守ることを目的としています。一般的に当事者同士が対等な立場で交渉できると考えられている事業者間の契約や別の法律で規定れている労働契約は、消費者契約法の対象外となります。
事業主は、消費者契約を知っておかなければ、一旦成立した契約が思いがけず取り消されたり、契約内容の一部が無効にもなってしいかねません。リスクを防止し、信頼を損なわないためにも消費者契約法を遵守しましょう。
消費者契約法で守られる消費者の権利と事業者の義務
取消権とは?
原則として、有効に成立した契約は、契約の当事者が一方的に取消すことができません。
そこで、消費者契約法では、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、事業者と消費者間の情報格差により、事業者の不当な行為によって契約した場合、その契約を取り消すことができることとしています(法4条)。
取消事由があれば、消費者は事業者に対して、取消事由を理由に事業者に契約を取消す旨の通知をすれば、契約をしたときにさかのぼって契約が無効となります。
取消権を行使することができる期間は、「追認をすることができる時から1年間(霊感商法の場合は3年間)」とされています(法7条)。しかし、「追認をすることができる時から1年間(霊感商法の場合は3年間)」であっても、契約の締結の時から5年(霊感商法の場合は10年)を経過したときは取消すことができなくなります(法7条)。
追認をすることができる時とは、取消事由が消滅し、かつ、取消権があることを知ったときの二つの要件を満たしたときのことをいいます(民124条)。
取消権を行使すると、消費者は契約をなかったことにでき、支払った代金の返還を求めることができます。事業者は、消費者が取消権を行使した場合、速やかに返金などの対応を行わなければなりません。
無効となる条項とは?
消費者契約法では、事業者の損害賠償の責任を免除する条項は無効とされています。
例えば、事業者の債務不履行により消費者に損害が発生した場合でも、事業者の責任を免除し、又は事業者がその責任の有無を決定する権限を付与する条項がこれにあたります(法8条1項1号)。
他にも、消費者の解除権を放棄させる条項は無効です。
消費者の解除権を制限する条項とは、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項のことをいいます(法8条の2)。
これらを含む無効となる条項は、消費者契約法によってすべてを明確に定められているわけではありません。裁判所の判例や解釈によって判断されることになります。
事業者の努力義務とは?
事業者と消費者間の契約は、事業者が契約内容を定めることが一般的です。そのため
消費者契約法では、事業者が、消費者に対して正確な情報を提供し、消費者が適切に判断できるよう事業者の努力義務を定めています。
具体的には、契約内容は、消費者が十分に理解できるよう、平易な言葉で分かりやすいものであること(法3条1項1号)、消費者の勧誘に際しては、個々の消費者の状況を総合的に考慮して契約内容について必要な情報を提供することが求められています(法3条1項2号)。他にも、消費者の求めがあったときは、消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供することが努力義務として規定されています(法3条1項4号)。
まとめ
消費者契約法は、特定の例外を除き、事業者と消費者の間で結ばれるほとんどすべての契約に適用されます。特定商取引法や割賦販売法など、事業者が守るべき法律はいくつかありますが、消費者契約法はそれらの基本となる土台のような存在です。だからこそ、事業者にとって消費者契約法の正しい理解は欠かせません。
消費者契約法で定められた取消事由に該当すれば、消費者は契約を取消すことができ、契約で定めた条項が無効になることもあります。
法令を正しく理解し、トラブルの予防と信頼性の高い事業運営を通じて、持続可能な事業経営につなげていきましょう。