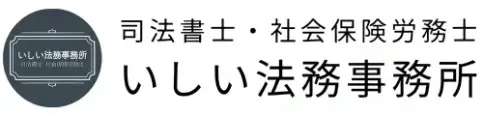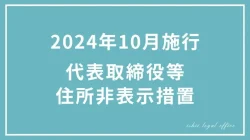遺言書の付言事項のポイントと文例まとめ
遺言書は、15歳以上の者であれば作成することができます。
そして、遺言書には付言事項を書くことができます。
では、付言事項とはどういうものなのでしょうか。
本記事では、付言事項の基本から簡単な文例まで詳しく解説します。
投稿者プロフィール
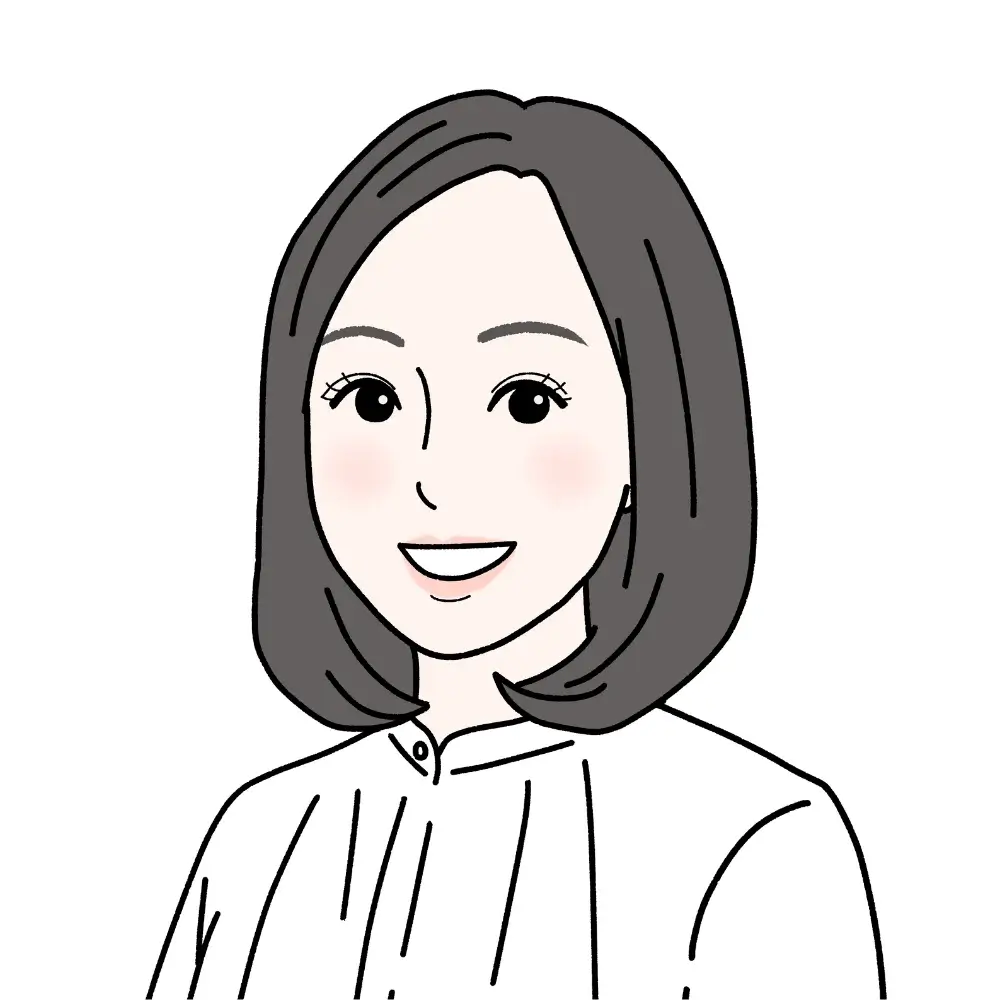
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
遺言書に付言事項を書く利点とは
付言事項は、遺言書の最後に書くことが多いですが、この付言事項は相続人を法的に拘束するものではありません。
付言事項を書く理由は、その内容により様々ですが、家族や大切な人に対する感謝の思いを伝えることができます。
そして、付言事項が、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現するための重要な手段となりえます。
例えば、特定の財産を特定の相続人に相続させる場合のように一見すると相続人間で不平等となるような遺言をするときは、
その理由や目的を付言事項に書くことで、相続人同士の不満や争いを防ぐ効果が期待できます。
このように、付言事項は、単に遺言者から相続人等へ感謝の気持ちを伝えるだけでなく、争いを防いだり、自分が亡くなった後の願いを伝える役目にもなります。
遺言書の付言事項に書く内容例
感謝の意を伝える
遺言は、人生の最後に残す大切なメッセージです。
生前伝えることができなかった、もしくは伝えていた相続人への感謝の気持ちを、改めて「文章」で伝えることができます。
例えば、長年支えられてきた感謝の気持ち、愛情をかけて育ててくれた感謝の気持ちなどを具体的に表現することで、遺言書が単なる財産分与の文書ではなく、遺言者から相続人への愛情のこもったメッセージになります。
付言事項の例
「妻の○○には、今までいろいろと苦労をかけました。長年連れ添ってくれてありがとう。私は〇〇と出会えて幸せでした。」
「私と、私の妻には子供がいませんでした。妻が亡くなった後は、私の弟〇〇の長女△△に大変お世話になりました。私は、△△に対し心から感謝しています。そこで、感謝の意を込めて私は遺言を残すことにしました。」
特定の財産分配理由を書く
特定の財産を相続人以外の者に遺贈する場合、その財産に対する思い入れや、贈与を受けた者に託したい願いなどを具体的に説明することで、相続人への配慮を示すことができます。
付言事項の例
「私は、生前、長男〇〇の妻である△△に大変お世話になりました。自宅の不動産は、長男夫婦が私と同居し、多くの思い出を共にした場所です。そこで、この自宅の不動産を長男と一緒にその妻△△にも遺贈することにしました。」
散骨を希望する
最近では、墓石を建てて納骨するのではなく、樹木葬や散骨などその様式も多様になってきました。
お墓に関する事項は、法的拘束力がありませんが、遺言を残すことで遺言者の希望を伝えることができます。
ただし、散骨については注意しなければなりません。
散骨そのものは違法でないこととされていますが、自治体で禁止していることもあるので実際に散骨をするときは確認が必要です。
付言事項の例
「私は、海が近くにある場所で生まれ、子供のころは海でよく泳いでいました。そして、私にはお墓を継ぐ人がいないため、散骨を希望します。」
「私は、山に散骨することを希望します。」
付言事項を書くときの注意点
否定的な感情を避ける
付言事項は、遺言者の思いを伝えるためのものですが、相続人に対する否定的な感情や批判的な言葉は避けた方がいいでしょう。
例えば、特定の相続人を非難したり、相続人の行動を批判したりするような内容は、相続人同士の感情的な対立を招き、相続トラブルの原因となる可能性があります。
遺言は、遺言者の最後のメッセージであり、相続人へ誤解を与えないような配慮も必要です。
遺言の内容の整合性を保つ
付言事項の内容が、遺言の内容と矛盾すると、混乱を招く原因になります。
遺言の内容と整合性を保ち、誤解を生じさせないようにしましょう。
付言事項は明確に丁寧な文章を心掛ける
付言事項には、決まった形式はありませんが、丁寧で理解しやすい文章で書くことが大切です。
複雑な文章は、読み手にとって理解しにくく、遺言者の意図が正確に伝わらず誤解を生じさせる可能性があります。
また、法的拘束力を持つ遺言内容と明確に区別して、読み手が混乱しないように書きましょう。
まとめ
遺言は、人生の最後に残す大切なメッセージです。
付言事項を記載することで、感謝の気持ちや意図を伝え、また、誤解よる相続人間の不要な紛争を回避することができます。
遺言書の作成は、法律的専門的な知識が必要となります。専門家に相談することで、より自分の想いのこもった遺言を正確に残すことができます。
遺言についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。