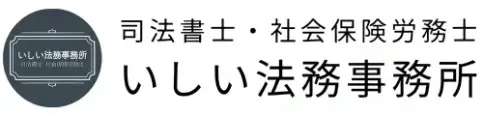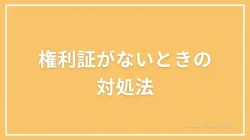合同会社の役員(社員)の退社
合同会社の役員は、合同会社の社員(株式会社でいうところの株主)でもあります。
社員の退社は、株式会社とは異なる手続きが必要となります。
合同会社の社員が退社する際、避けて通れないのが退社する社員が有する「持分(株式会社でいう株にあたるもの)」がどうなるかについてです。
この記事では、合同会社の社員の退社について解説します。
投稿者プロフィール
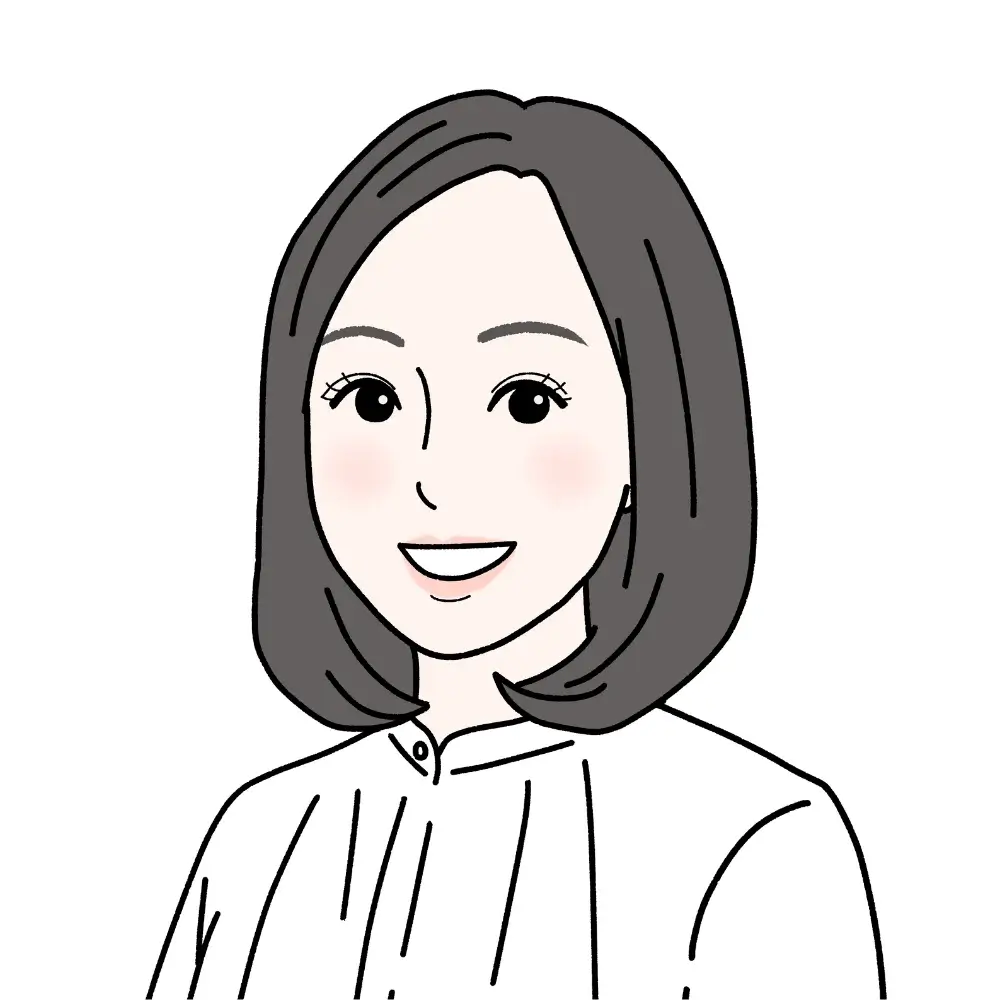
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
合同会社の社員の退社に関する基本知識
合同会社は、株式会社と異なり、出資と経営が一致する点が特徴となります。
この点が、社員の退社に影響を与えるため、注意が必要です。
任意退社
合同会社の社員の退社には、主に、社員の意思による任意退社と、法律で定められた法定退社、持分の全部譲渡よる退社があります。
任意退社は、社員が自らの一方の意思で会社を辞めることを指します。
各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます(会606条3項)。
逆をいえば、やむ得ない事由がなければ任意退社できないこととなりますが、定款で別段の定めを設けることができるとされています(会606条2項)。
また、①合同会社の存続期間を定款で定めなかったとき、または、②ある社員の終身の間合同会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、6か月前までに合同会社に退社の予告をしたうえで、事業年度の終了の時において退社をすることができます(会606条1項)。
法定退社
法定退社は、次に掲げる事由により、社員の地位を失うことを指します(会607条)。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡
- 合併(社員が法人で、合併により当該法人である社員が消滅する場合)
- 破産手続開始の決定
- 後見開始の審判を受けたこと
- 除名
法定退社に該当するときであっても、
破産手続開始の決定、解散、後見開始の審判を受けたこと、除名については退社しない旨を定款で定めることができるとされています。
持分全部譲渡
合同会社の社員は持分を有しています。
社員は、原則、他の社員の全員の承諾があれば、その持分の全部又は一部を第三者に譲渡することができます(会585条)。
その持分の全部を第三者に譲渡した場合は、持分を譲渡した社員は退社することになります。
譲渡により持分を取得した第三者が、新たに合同会社の持分を有することとなるときは、その持分を取得した第三者は新たに社員となります。
持分の譲渡により、税金が発生することがありますので、事前に税金の専門家に相談されることをお勧めします。
退社する社員の持分
持分の払戻しと債権者保護手続き
退社した社員は、その出資の種類を問わず、金銭でその持分の払戻しを受けることができます(会611条1項、3項)。
当然といえますが、持分の全部を第三者に譲渡した場合は、持分の払戻しを受けることはできません。
退社した社員の持分の計算は、退社の時における合同会社の財産の状況に従ってしなければなりません(会611条2項)。
そして、持分の払戻しのために減少する資本金の額は、持分の払戻しにより退社した社員に交付する金銭等の帳簿価額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならないこととなっています(会626条3項)。
持分の払戻しにより資本金が減少するときは、債権者保護手続きが必要となります。
具体的には、官報への公告と債権者への各別の催告が必要になります(会627条)。
また、合同会社が持分の払戻しにより退社した社員に交付する金銭等の帳簿価額がその持分の払戻しをする日における剰余金額を超えるときにも債権者保護手続きが必要になります(会635条)。
このように、退社による持分の払戻しをするときは、合同会社の状況により債権者保護手続きが必要になったり、税金が発生することがあります。
まとめ
合同会社の社員は株式会社と異なり持分を有していますので、社員の退社時はその持分についても考慮が必要になります。
また、合同会社の状況により税金が発生することもあります。
会社の状況や定款の内容、登記手続き、債権者保護手続きなども大切ですが、同時に税金面への考慮も必要です。
当事務所は、ご相談者様の顧問税理士と連携させていただくこともできますし、ご紹介することもできます。
ご不安なことやご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。