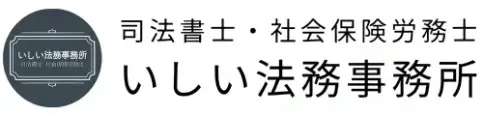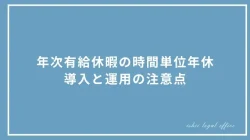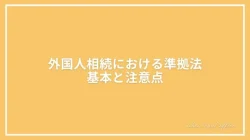就業規則への明記が必須?有給の計画的付与制度導入ガイド
年次有給休暇の計画的付与制度は、従業員の休暇取得を促進するために導入された制度です。この制度は、従業員のワークライフバランスを改善しつつ、企業の労務管理コストの削減、円滑な業務運営が期待されます。本記事では、制度導入の手順から、労使協定の締結、注意点までを解説します。
投稿者プロフィール
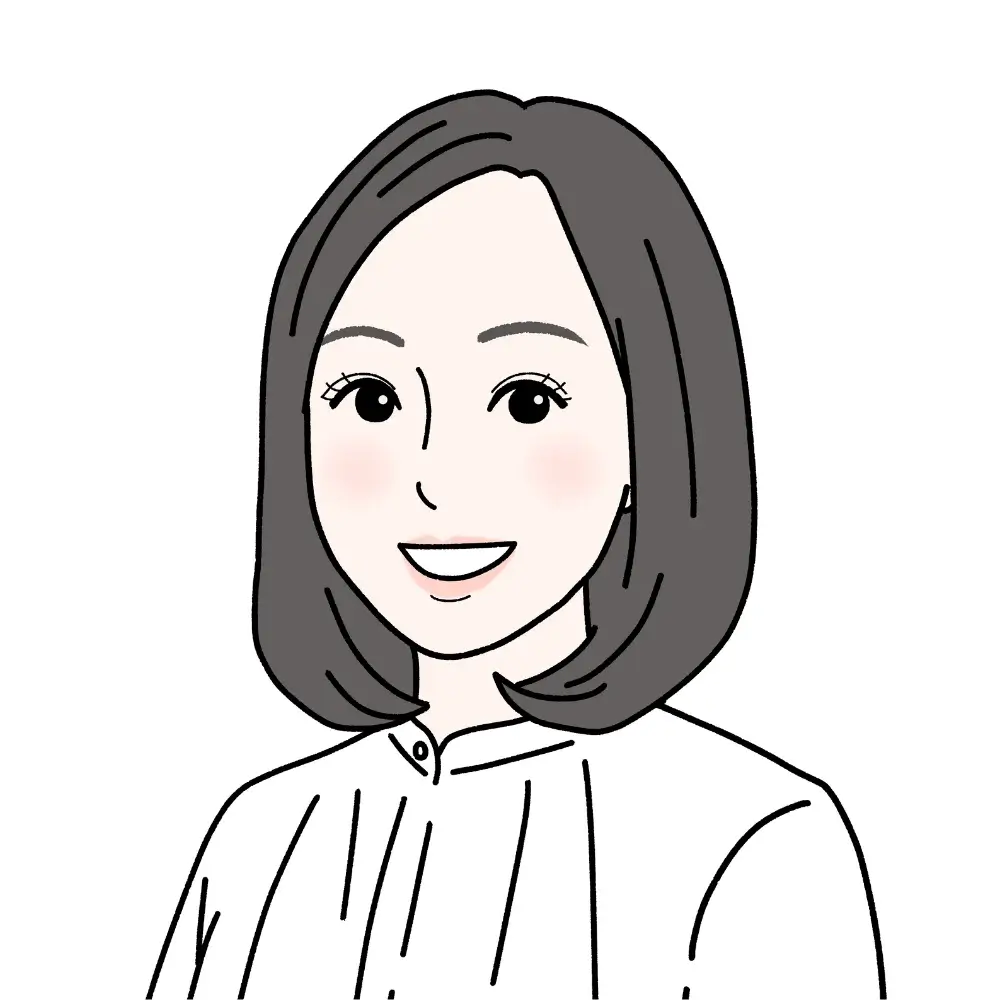
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
年次有給休暇の計画的付与とは?
年次有給休暇の計画的付与制度は、従業員が保有する年次有給休暇の一部について、労使協定に基づき企業が計画的に付与日を指定できる制度です(労働基準法第39条第6項)。
この制度の導入により、従業員の休暇取得を促進できるだけでなく、企業側も業務の繁閑に応じた効率的な労務管理が可能になります。結果として、ワークライフバランスの向上や職場定着率の改善といった効果が期待されます。
制度導入のメリットと対象企業の特徴
制度を導入するにあたっては、労使間での十分な協議を行い、従業員の意見を反映させることが大切です。計画的な休暇取得を促進することで、企業には労務管理がしやすく計画的な業務運営が可能になります。また、より働きやすい職場環境を実現し、従業員の定着率の改善に繋がることが期待されます。
計画的付与制度は、特定の業種や規模の企業だけでなく、様々な企業で導入可能ですが、特に、業務の繁閑の差が大きい企業や、従業員の休暇取得率が低い企業にとって有効です。たとえば、サービス業においては、業務が忙しくない時期に計画的に休暇を付与することで、従業員の負担を軽減し、サービスの質を維持することができます。
計画的付与は、従業員ごとに付与日を指定することもできます。従業員ごとに柔軟に日程を決めることも可能なため、自社の業態や勤務形態に合わせた導入が可能です。
導入前に確認しておくべき法的ルール
年次有給休暇の計画的付与制度を導入するにあたっては、労働基準法をはじめとする関連法規を遵守しなければなりません。
年次有給休暇の取得は、原則として従業員の自由な意思に委ねられるべきものとされています。しかし、労使協定を締結することで、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、企業が計画的に付与日を指定することが可能になります。言い換えると、年次有給休暇のうち最低でも5日は、従業員が自由に使える年次有給休暇として残しておく必要があります。
また、計画的付与制度の導入したときは、就業規則の絶対的記載事項になるので、その旨を明記しなければなりません。
まとめると、以下の法的要件に注意が必要です。
- 計画的に付与できるのは「5日を超える分」のみ(労働基準法上、5日は従業員の自由取得が必要)
- 労使協定の締結が必須
- 就業規則の絶対的記載事項として、計画的付与制度の導入を明記する必要あり
制度導入時の注意点と対応策
1.年次有給休暇が少ない従業員への配慮
計画的付与制度の趣旨は、従業員の休暇取得を促進することですが、事業主は、年次有給休暇が少ない従業員に対して、特別な配慮を行わなければならないことがあります。
前述したとおり、年次有給休暇のうち最低でも5日は、従業員が自由に使える年次有給休暇として残しておかなければなりません。しかし、計画的付与の対象となる日数に5日を加えた日数が、従業員の年次有給休暇の日数を超える場合は、その従業員に計画的付与を行うと、従業員が自由に使える年次有給休暇が5日よりも少なくなってしまいます。
そのため、一斉に計画的付与を行う場合は、そのような従業員に対し、特別に年次有給休暇を付与する、または休業手当として平均賃金の60%以上を支払うなどの対応が必要となります。
ただし、従業員個別に日程を指定する形式であれば、対象外とすることでも対応可能です。
2.計画的付与日前に退職する従業員への対応
計画的付与日が来る前に退職する場合でも、予定されていた有給日数の取得を認める義務があります。退職する従業員は、計画的付与としていた日数も、退職までに取得することが可能です。
労使協定の締結|スムーズな制度導入のために
労使協定とは?締結の意義と法的必要性
年次有給休暇の計画的付与制度を導入するには、労働基準法第39条第6項に基づき、労使協定の締結が必須です。これにより、企業は5日を超える年次有給休暇について、計画的に取得日を指定できるようになります。
労使協定とは、会社と、事業場の過半数労働者を代表する者(または労働組合)との間で交わす書面による合意のことです。労働基準監督署への届出は不要ですが、社内で適切に保管する必要があります。
協定書に盛り込むべき主な項目
計画的付与に関する労使協定には、以下の内容を明記しましょう。
- 計画的付与の対象となる従業員の範囲
例:育児休業中や定年退職予定者を除外する - 計画的付与の対象となる日数
- 計画的付与の具体的な方法(以下の3つのいずれか)
①事業場全体の休業による一斉付与の場合
②班やグループ単位で交替制付与
③個人別に付与(年休計画表を作成やその手続き) - 年次有給休暇の日数が少ない従業員の扱い
- あらかじめ計画的付与日の変更が予想される場合は、変更する場合の変更手続き
協定内容は、従業員の状況や事業形態に応じて柔軟に設定することが大切です
まとめ|計画的付与の導入で働きやすい職場づくりを
有給休暇の計画的付与制度は、企業と従業員双方にとってメリットがある制度です。しかし、導入には労使協定の締結や就業規則の改定など、法的な要件や実務対応が必要不可欠です。
企業の状況に合わせて柔軟に制度設計を行い、従業員の理解と納得を得ながら、働きやすい職場づくりを進めていきましょう。
制度の導入・就業規則の整備に不安がある場合は、社会保険労務士など専門家への相談をおすすめします。