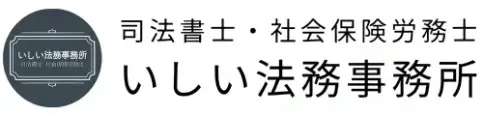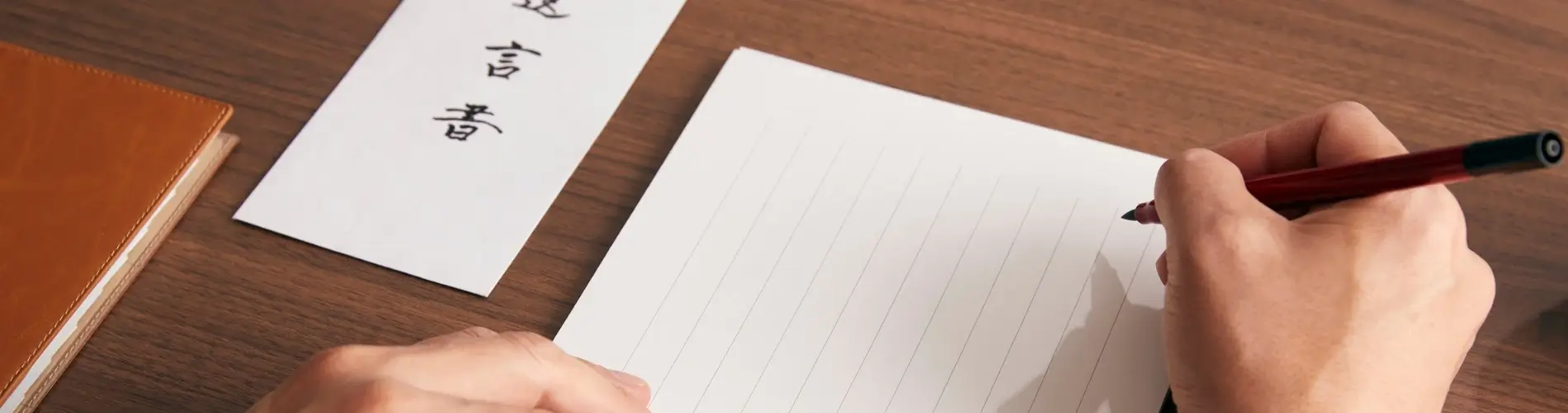
大切な人へ、きちんと想いを届けるために
あなたらしい「遺言書」作成をサポートします
こんなお悩みありませんか?
- 万が一のとき、子どもたちに負担をかけたくない
- 自分が亡くなったあと、家族がもめないか心配
- 子どもがいないので、財産を誰に渡すか決めておきたい
- 再婚していて、前の家族・今の家族の間でトラブルにならないか不安
- 独身なので、将来、財産をどうすべきか悩んでいる
今のうちに「想いを形にする準備」を始めてみませんか?
当事務所が最適な遺言書作成を、丁寧にサポートいたします。
ご相談は、まだ漠然としたお悩みでも大丈夫です。
まずはお気軽にお話をお聞かせください。
でも、
「今は元気だから、遺言書なんてまだ必要ない」
そう考える方は多くいらっしゃいます。
なぜなら、遺言書は、
- 「自分が亡くなった後」のことを考える作業であり、
- 何をどう書いていいかわからない漠然とした不安を感じたり、
- 公正証書にするのって大変そうと感じたり、
- 一度書いたら変えられないと思っていたり、
- なにより「まだ元気だからいいや」と思ってしまうものだからです。

でも実際には、元気なうちに遺言書を作っておくことで、自分や残される家族の心の負担が軽くなることがあります。
遺言書は、財産の分け方を決めるためだけのものではありません。
「ありがとう」「これからも見守っているよ」そんな言葉を託すこともできる、大切な想いの手紙です。
専門家と一緒なら、初めてでも大丈夫です
遺言書について、
「何をどう書けばいいのか分からない」
「うちの場合、遺言って必要なのかな?」
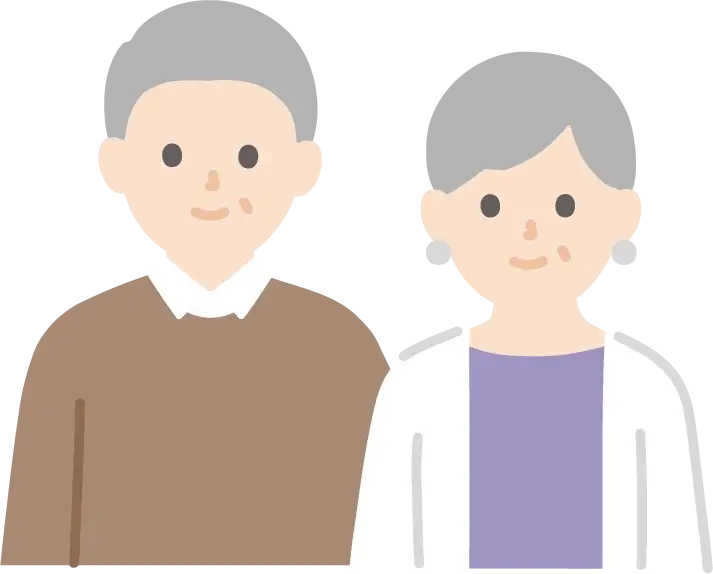
そうした疑問にひとつずつ丁寧に向き合いながら、あなたに合った遺言書の形をご提案します。
- 将来の相続手続きがスムーズになる内容
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いかの判断 など
司法書士として、法律的な視点はもちろん、ご家族の関係性や想いも大切にしながらサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
【遺言書作成サポートを受ける3つのメリット】
遺言書は、「残された人のため」に作るもの。
しかし、せっかく作成しても、
・形式の不備で無効になってしまう
・内容があいまいで、家族がもめてしまう
・相続手続きが複雑になってしまう
といったことにもなり得ます
1. 家族の誤解を生じない遺言
法的に有効でも、内容によっては(表現が曖昧など)相続トラブルの原因になってしまうことも考えられます。
法律の専門家として、遺言の内容設計からお手伝いします。
2. 想いを言葉にするサポート
「何をどう書けばいいのか分からない」
そんな方もご安心ください。
ご家族へのメッセージや想いの整理を、丁寧にヒアリングしながら形にします。
3. 不動産登記の専門家
相続財産には、不動産が含まれることが多いです。
相続が発生したら、名義変更(相続登記)が必要になります。
司法書士は登記の専門家です。遺言書の作成段階から相続登記手続きのことまで考え、より良い遺言書作成のサポートをいたします。
このような方に、特にご相談いただいています
- 子どもがいない
- 再婚しており、前妻との子もいる
- 自宅の名義や預金の分け方が心配
- 将来、家族が相続手続きで困らないようにしたい
どんな些細なご相談でも大丈夫です。まずはお気軽にご連絡ください。
司法書士がすすめる、遺言書を作成した方がいい人チェックリスト
- 子どもや親族とは疎遠である
- 再婚しており、前の配偶者との間に子どもがいる
- 子どもがいない(夫婦のみ or 兄弟姉妹が相続人になる)
- 財産の大半が不動産である(分けにくい)
- 相続人以外(内縁の妻・子の配偶者など)に財産を残したい
- 障がいのある子どもや、高齢の配偶者がいる
- 家業や事業を引き継がせたい相手が決まっている
- 特定の相続人に多く(または少なく)渡したいと考えている
- 自分の気持ちや感謝を、文章として家族に伝えたい
- 相続手続きで家族に負担やトラブルをかけたくない
- 過去に相続でトラブルを経験したことがある
遺言書は「まだ早い」と思われがちですが、 実際に元気な今だからこそ作れるものです。
しっかりサポートいたしますので、「何から始めればいいか分からない」方も、まずはお話をお聞かせください。
遺言の種類とサポート内容
遺言書には大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、相談者がご自身に合った方法を選択できるようご案内します。
【サポート内容(一例)】
・遺言内容のヒアリングとアドバイス
・文案作成サポートおよびチェック
・公証人とのやりとり代行(公正証書遺言の場合)
・証人の手配
・遺言執行者のご相談
・自筆証書遺言書保管制度のご案内 など
遺言書作成までの流れ(公正証書遺言の場合)
公正証書遺言を前提に一般的な流れについて説明します
Step1 相談・ヒアリング(初回相談無料)
遺言書を作成する目的やご希望をお伺いします。
・「誰に、何を、どう渡したいか?」
・推定相続人が誰になるのか、不動産や預金の内容など
不安や疑問を整理して、「どういう遺言が自分に合っているか」一緒に考えます
ご希望であれば見積書を作成いたします。
ここで依頼するかどうかを決めていただいても問題ありません。
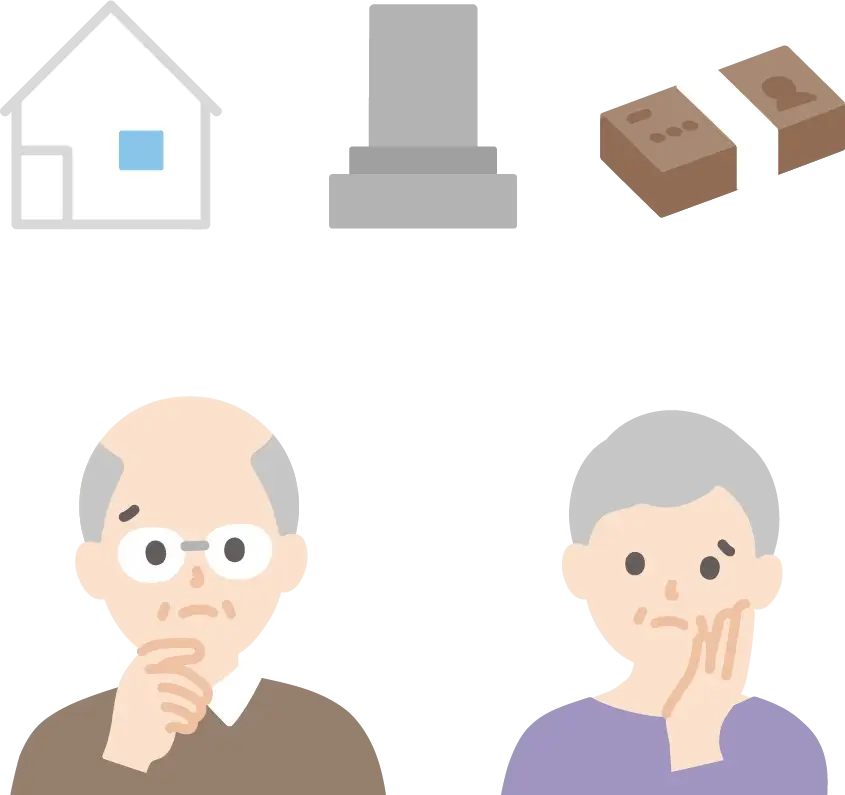
Step2 原案の作成・確認
ヒアリングのもと、遺言者と一緒に遺言の内容を考え、その内容を文章にします。
内容を相談しながら、何度か修正を重ねて「納得できる形」に仕上げていきます。

Step3 公証人との調整・予約
最終案が固まったら、公証人に内容を伝えて最終文案を作成してもらい、予約を取ります。
公証人との調整・予約は、当事務所で代行いたします。

Step4 公正証書遺言の作成(当日)
公証役場(※)で、本人+証人2名+公証人の立ち合いで作成します。
証人は、次の人はなることができません。
・推定相続人
・受遺者
・上記の者の配偶者や直系血族
当事務所で証人をご用意することもできますので、ご安心ください。
本人の意思能力が確認され、内容を読み上げられた上で本人+証人2名が署名・押印します。
※公証人に出張してもらうこともできます(出張費用がかかります)
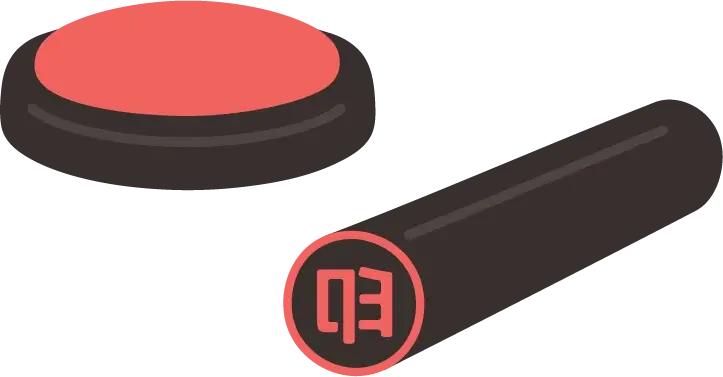
Step5 遺言書完成・保管
公正証書遺言は原本を公証役場が保管(※)してくれます。
遺言者には「正本」「謄本」の2通が渡されます。
1通は自分で保管をし、もう1通は物理的に離れた場所で保管したり、遺言執行者に預けるとより安心です。
※保管期間は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間とされています

遺言書作成サポートFAQ
(よくあるご質問)
-
遺言書が完成するまで時間はどれくらいかかりますか?
-
簡単な内容であれば、早ければ1~2週間程度、内容が複雑な場合や関係者が多い場合は1か月以上かかることもあります。
-
遺言書って、どんな人が作るべきですか?
-
ご高齢の方だけでなく、子どもがいないご夫婦、再婚をしている方、特定の人に財産を渡したい(例:長年介護してくれた方、内縁の配偶者など)方などです。
遺言書を作成することに大きな負担を感じられる方は、無理に作成する必要はないと考えています。
-
自分で書く「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はどう違うのですか?
-
相続発生後の法的効力としては同じです。
ただし、公正証書遺言は、形式不備による無効、紛失や偽造の恐れを避けることができ、証明力が高いとされています。また、相続発生後の検認が不要になります。
-
遺言書を書いたことを、家族に伝えるべきですか?
-
原則として伝えておく方が良いですが、伝えたくない場合でも問題ありません。
特に公正証書遺言であれば、本人が亡くなったあと、遺族が公証役場で遺言書の確認ができます。
伝える・伝えないも含めて、相談時に一緒に考えていきましょう。
-
書いたあとの内容を変更したくなったらどうすれば?
-
遺言書は、いつでも書き直しが可能です。公正証書遺言であっても同じです。内容が重複する部分については最新の日付のものが有効となりますので、状況の変化に応じて必要があれば書き直しをしましょう。
当事務所では、定期的な見直し相談にも対応しています。
-
相続人以外の人(たとえば友人や寄付先)に財産を渡すことはできますか?
-
はい、可能です。
ただし、遺留分という「法定相続人が最低限受けられる権利」があるため、注意が必要です。ご希望を叶えるようにサポートいたします。
遺言書を「きちんと残す」は、「きちんと託す」こと
遺言書は、ご自身の意思を確実に伝えるための法律文書です。
まだ具体的に決まっていなくても大丈夫です。
「こんなことで相談していいのかな?」というお悩みでも、どうぞ遠慮なくお話をお聞かせください。
あなたと、ご家族にとっていちばんよい形を一緒に考えていきましょう。
専門家として、「安心」を形にいたします。
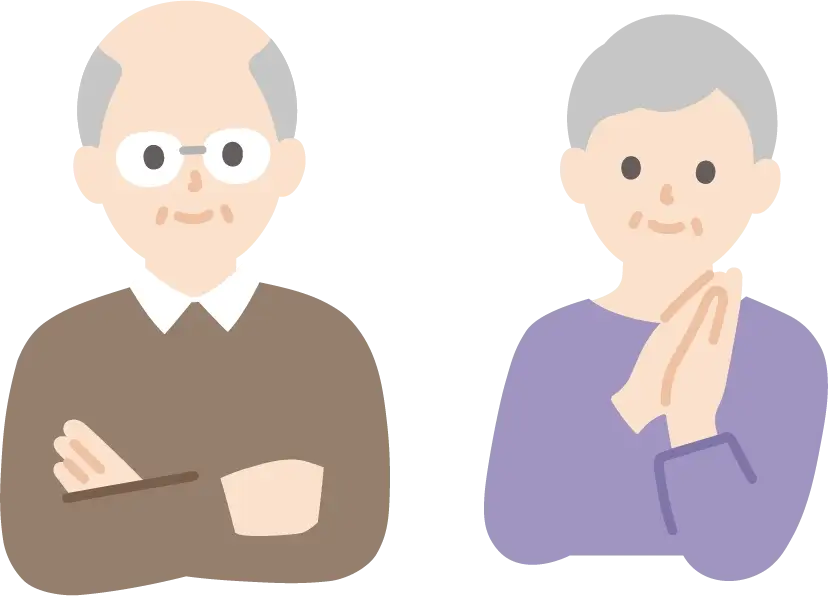
まずはお気軽に無料相談をお受けください。