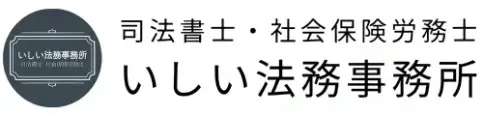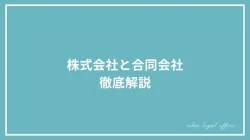自筆証書遺言書保管制度 と 公正証書遺言|どちらが最適か?
相続トラブルを未然に防ぐ手段として、遺言書の作成は非常に重要です。しかし、「どの方法で遺言書を作成すべきか」「どこに保管するのが安全か」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「自筆証書遺言書保管制度」と「公正証書遺言」という代表的な2つの遺言方法の違いや、それぞれのメリット・注意点をわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール
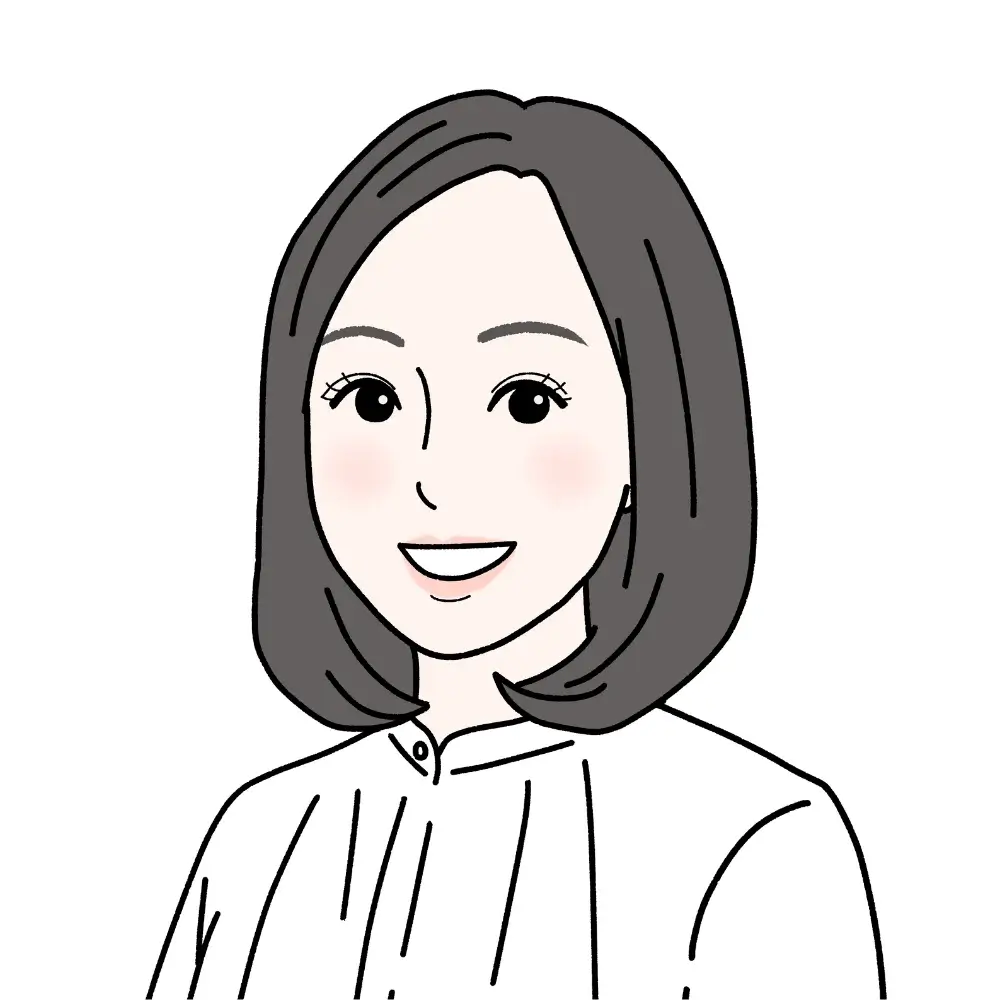
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度の概要
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月に施行された新しい制度で、自筆で作成した遺言書を法務局が安全に保管する制度です。自宅で保管する場合に起こりがちな「紛失」「改ざん」「遺言書の発見が遅れる」といったリスクを減らすことができます。
法務局に保管された遺言書は、遺言者の死後、相続人に通知される仕組みも整っており、遺言書の存在を確実に伝えたい方には安心です。
利用方法と費用
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、法務局に予約をして、遺言書の保管の申請をする必要があります。
申請には、申請書、遺言書原本、住民票の写し(本籍と戸籍の筆頭者の記載のあるもの)、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類、手数料が必要です。
遺言書は、遺言者が自筆で作成し、自筆証書遺言書保管制度を利用するに必要な一定の様式が満たされたものでなければなりません。
申請にかかる費用は3,900円で、収入印紙で支払います。
申請手続きは、必ず本人が法務局の窓口で行わなければいけないこととされています。
保管の申請をすることができる法務局は、次の3つのいずれかを管轄する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
制度利用時の注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットは、遺言書の紛失や破棄のリスクを減らすことができる点です。
また、死亡した時に遺言書の存在を相続人に通知することもできます。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用する際には注意すべき点もあります。
まず、遺言書の内容が法律的に有効かどうかは、法務局ではチェックされません。そのため、遺言書の内容が法律的に有効かどうかは、自己責任となります。遺言書の内容が遺言者の意図しない表現となっている場合、「争族」となるのを未然に防ぐために作成した遺言書が、逆に相続人間で争う原因になることもあります。遺言書の内容についてご不安な場合は、司法書士や弁護士などの専門職に相談するのがおすすめです。
また、前提として、遺言書は民法で定められた形式的要件を満たしたものである必要があります(民法968条)。
さらに、用紙の周りに一定の余白が必要など、保管制度を利用するための様式に合わせた遺言書を作成する必要があるので注意が必要です。
保管された遺言書の原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは死亡後150年間保管されることになっています。長期間にわたり信頼性の高い保管が可能です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記し、証人2名の立会いのもとで内容を確認・承認した後署名し、印を押すこととされています(民法969条)。
自筆証書遺言と異なり、内容の法的有効性や本人の意思確認が行われるため、トラブルのリスクが極めて低く、「確実に遺志を残したい方」に適しています。
作成時には、印鑑登録証明書(3か月以内)・戸籍謄本・登記簿謄本・評価証明書・預貯金通帳など、相続内容に応じた書類が必要です。
通常、遺言書の正本と謄本の各1通が遺言者に交付されます。公正証書遺言の保管期間は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存するとされています。
費用は遺言内容や財産額により異なりますが、数万円からとなります。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
検認が不要になる
通常の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に遺言書を保管しておけば、検認が不要になります。
この制度は、相続人が遺言の存在や内容を確実に把握できるようにするため、スムーズな相続手続きを可能にします。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
(裁判所HPより引用)
なお、公正証書遺言も検認不要であるため、手続きを簡素化したい方にはどちらも有効です。
紛失・隠匿・改ざんのリスクを軽減
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿、破棄のリスクを大幅に減少させることができます。
遺言書を自宅で保管していると、紛失したり、隠匿されたり、破棄されたりするリスクがあります。
悲しいことですが、相続人の中に遺言書の存在を知らない相続人がいる場合、遺言書が隠匿される可能性ないともいえません。
また、遺言書が紛失した場合、相続手続きが複雑化し、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局に保管されるため、このようなリスクを軽減することができます。
相続人などへの確実な通知
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言者の死亡後に法務局が相続人へ遺言書の存在を通知してくれます。
これにより、「遺言書の存在を知らなかった」「知らされていればトラブルにならなかった」といった事態を防ぐことができます。
通知機能があることで、相続トラブルの防止や相続手続きの円滑化に大きく寄与します。
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
内容の有効性チェックがされない
この制度を利用しても、遺言書の内容が法的に有効かどうかを法務局が判断することはありません。
形式が整っていても、記載内容に法的な不備があれば、相続トラブルの原因になってしまうこともあります。
特に遺産分割の方法や相続人以外への遺贈が含まれる場合には、司法書士や弁護士など専門家の確認を受けることが重要です。
自筆証書遺言の作成では公正証書遺言のように公証人の意思確認や証人が立ち会いがあるわけではありません。そのため、公正証書遺言よりも証明力が一般的に低いとされています。
自筆での作成が必要
自筆証書遺言では、財産目録以外は全文を本人が手書きする必要があります(民法968条)。高齢の方や手が不自由な方、字を書くのが難しい方にとっては大きなハードルになります。
一方、公正証書遺言では自筆は不要であり、高齢者や障がいのある方でも安心して作成できます。
法務局に本人が出向く必要がある
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、本人が法務局の窓口に直接出向く必要があります。
一方で、公正証書遺言の場合は、公証人に自宅や病院まで来てもらうことが可能です(出張費は発生)。体調や事情により外出が難しい方にとっては、公正証書遺言の方が柔軟な対応が可能といえるでしょう。
公正証書遺言との比較|費用・信頼性・通知・出向の違いを解説
遺言書の作成方法として、「自筆証書遺言書保管制度」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶべきか迷われる方も多いでしょう。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、最適な選び方についてご紹介します。
費用面の違い|コストを抑えたいなら自筆証書遺言
自筆証書遺言書保管制度は、保管手数料が3,900円と非常に安価で済む点が魅力です。
一方、公正証書遺言は内容や財産の額に応じて数万円から十数万円の費用がかかるのが一般的です。
そのため、コストを重視したい方や比較的シンプルな内容の遺言を希望される方には、自筆証書遺言書保管制度が適しています。
内容の確実性|トラブル防止なら公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思確認を行い、証人2名の立会いのもとで作成されるため、証明力が非常に高いとされています。
万が一、相続人間で争いが起きた場合にも、公正証書遺言は法的効力が強く、裁判でも有利に働く可能性があります。
一方、自筆証書遺言書保管制度では、法務局は遺言書の形式面しか確認しません。内容が法律上無効であっても、そのまま保管されてしまうため、事前に司法書士など専門家によるチェックが不可欠です
通知サービスの有無
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言者が亡くなった後、法務局が相続人に遺言書の存在を通知してくれます。
これにより、「遺言書の存在に気づかなかった」「故意に隠されてしまった」といったリスクを回避できます。
対して、公正証書遺言には自動的な通知制度はありません。そのため、信頼できる相続人や第三者(司法書士・弁護士など)に遺言書の保管場所や内容をあらかじめ伝えておく工夫が必要です。
出向の要否|柔軟な対応が可能な公正証書遺言
自筆証書遺言書保管制度では、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。
一方、公正証書遺言は、公証人が自宅や病院などに出張して対応することが可能なため、身体が不自由な方や入院中の方でも安心して作成できます。
まとめ
「費用を抑えつつ、形式的なミスなく遺言を残したい」という方には、自筆証書遺言書保管制度が有効です。
一方で、「相続トラブルを避けたい」「内容に複雑な要素がある」「字を書くのが難しい」という方には、公正証書遺言の方が信頼性が高く、柔軟に対応できる点で優れています。
いずれの方法でも、遺言書はあなたの最期の意思を形にし、家族の安心を守る大切な手段です。
自分に合った遺言の方式を選び、ご不安があれば司法書士や弁護士など専門家のサポートを受けましょう。