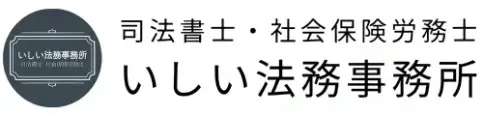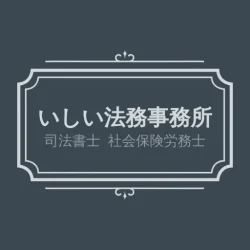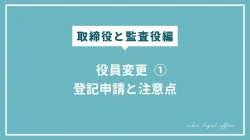相続した不動産、名義変更しないとどうなる?放置リスクと正しい手続き
「父から不動産を相続したけれど、そのままになっている…」
「固定資産税は払っているけど、名義って変えないといけないの?」
このように、相続した不動産の名義をそのままにしている方は少なくありません。しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、放置していると過料(罰金)の対象となる可能性があります。さらに、名義変更しないことで将来的に大きなトラブルにつながるリスクもあります。
この記事では、不動産を相続した際の名義変更の必要性と放置するリスク、正しい手続きについて、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール
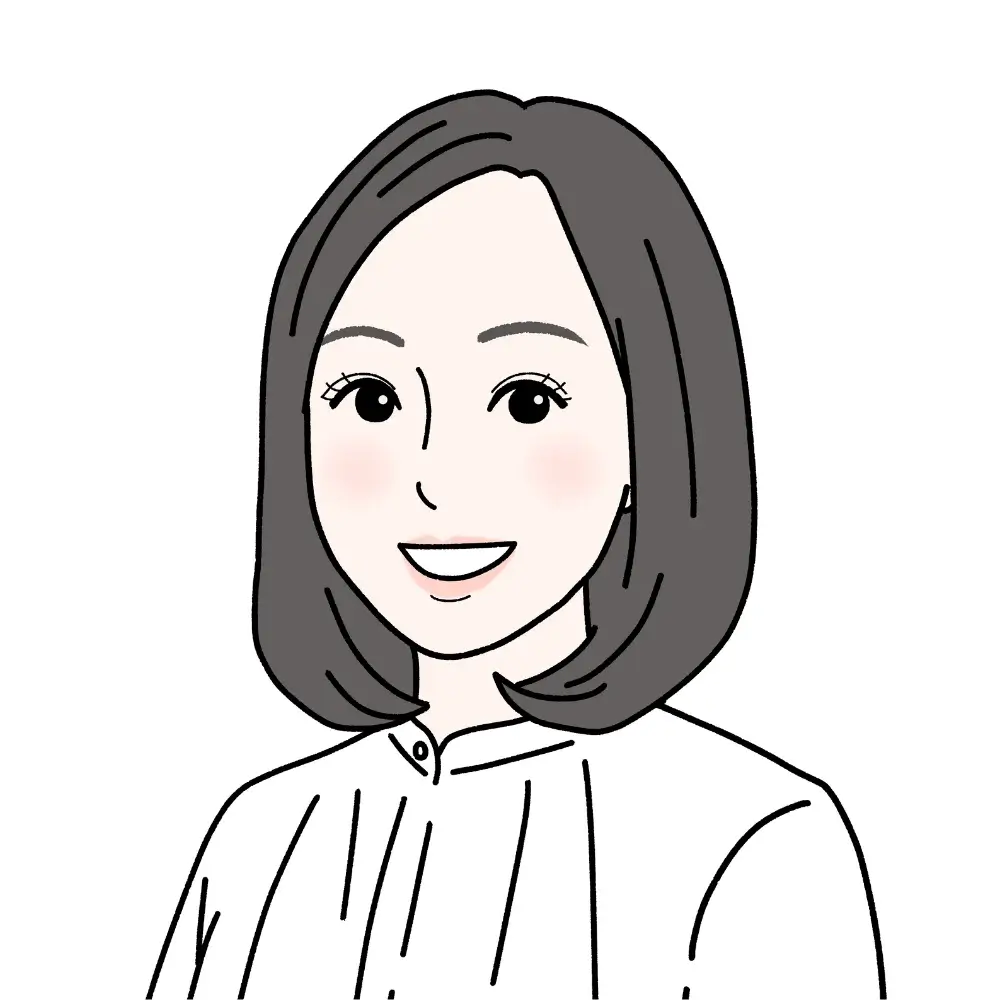
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
相続した不動産を名義変更しないと、こんなトラブルが
「名義変更しなくても、今は困っていない」
実際、そのような方が多いのが現状かもしれません。しかし、不動産の名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、次のような問題が起きやすくなります。
・不動産を売却できない・銀行から借入れする際の担保にできない
・相続人が複数いる場合、意見が割れたときや相続人の中に高齢な方がいるときは調整が難しくなる
・さらに相続が発生すると、関係者が増え登記が複雑になる
たとえば、「祖父の名義のまま放置していた実家を売ろうとしたが、相続人が10人以上になっており、調整に何年もかかってしまった」という事例もあります。
不動産を売却・担保にできない
不動産の名義が被相続人のままでは、不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。不動産を売却するには、まず相続登記を行い、自分の名義に変更する必要があります。
また、金融機関から融資を受けるために不動産を担保に入れる場合も、同様に相続登記が必要となります。金融機関は、担保となる不動産の所有者が明確であることを重視します。そのため、資金が必要になった際に、不動産を活用することができなくなります。
急な出費が必要になった場合や、事業資金を調達したい場合など、不動産を売却したり、担保に入れたりすることで資金を調達することを検討している場合は、早めに相続登記を行うことが重要です。相続登記を放置していると、いざという時に不動産を活用できず、資金繰りに困窮する可能性があります。
遺産分割協議の成立が難しくなる
Aさんの相続人が、配偶者B、子C、子Dの3人で、Aさんの遺言書がなかったとします。相続不動産を法定相続分ではなく子C一人に不動産を取得させたい場合、3人で遺産分割協議をすることになります。
では、相続登記をしない間に、ご高齢のBが認知症にかかり、判断能力が著しく低下してしまった場合はどうなるでしょうか?
認知症などによって意思能力を喪失した相続人は遺産分割協議をすることができません。認知症などによる意思能力のない者と遺産分割協議をする場合は、成年後見制度を利用して、成年後見人つける必要があります。
しかし、成年後見人は、認知症となった本人の財産を守る立場にあるので、本人が取得する財産が法定相続分以下となってしまうような内容の協議をすることが難しくなってしまいます。
また、連絡が取れない相続人がいる場合は、不在者財産管理人を選任する必要があります。不在者財産管理人は、家庭裁判所で選任され、連絡が取れない相続人の財産を管理し、遺産分割協議に参加することになります。これらの手続きは、時間と手間と費用がかかるため、相続登記を放置している期間が長くなるほど、手続きが複雑化する可能性があります。
相続人が増え相続関係が複雑になる
相続登記を放置すると、時間が経つにつれて相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。
例えば、不動産の名義人であるAさんが亡くなりました。Aさんの相続人は、配偶者B、子C、子Dの3人だったとします。
しかし、相続登記をしないうちにAの相続人である子Dが亡くなってしまいました。Dの相続人はDの子E、子Fだったとします。
Dが亡くなる前に相続登記の手続きをしておけば、BとC、Dの3人の話し合いで手続きを進めることができたのですが、Dが亡くなった後だと、B、C、E、F4人の話し合いで相続登記を進めなければなりません。
相続登記をしようとしたとしても、E、Fがどこに住んでいるのかも分からず、分かったとしても、関係者間で合意形成が難しくなることも考えられます。
相続登記の義務化とは?罰則もあります
2024年4月から、相続(遺言も含む)によって取得した不動産は原則として「不動産を取得した相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内」に登記申請しなければならないと法律で定められました。正当な理由がなく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これは、「相続不動産の放置」が年々増加し、空き家問題や所有者不明土地問題の原因となっていることへの対策として導入された制度です。
名義変更の手続きと必要書類
不動産の名義変更には、一般的には以下のような手続きと書類が必要です。
【主な必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・被相続人の死亡時の住所がわかるもの(住民票の除票)
・相続人全員の戸籍謄本と住民票
・遺産分割協議書または遺言書
・不動産の固定資産評価証明書
・登記申請書類
【手続きの流れ】
- 遺言書の有無
- 必要書類の収集
- 相続人の確定
- 相続人間での話し合い(遺産分割協議)
- 登記申請書の作成・提出
専門家に依頼するメリットとは?
相続登記の手続きは、自分ですることができます。しかし、相続人の確定や戸籍の収集、協議書の作成、円滑で不備のない登記申請には専門知識が必要になります。
以下のようなケースでは、司法書士に依頼することで、手間やトラブルを回避できます。
・相続人が遠方に住んでいる
・連絡が取りづらい
・不動産が複数ある
・遺言書があるが内容が複雑
・名義変更と一緒に売却や活用を考えていて急いでいる
当事務所では、これらの手続きを一括してサポートしております。当事務所は、神戸市東灘区・芦屋エリアを中心に、相続や登記の手続きを多数ご依頼いただいております。
以下のような点で、安心してご相談いただけます。
・女性司法書士が親身に対応
・全国対応・オンライン相談も可能
・相続登記に加え、相続放棄や遺言なども一括対応
・初回相談無料。手続きの流れや費用も丁寧にご説明
「こんな場合でも大丈夫?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
まとめ|早めの名義変更が、家族を守ります
相続した不動産の名義変更は、「急がなくても大丈夫」と思いがちですが、実は放置している間にリスクが増えていきます。
義務化された今、「やっておけばよかった」と後悔する前に、相続登記をしておきましょう。相続について不安がある場合は、まずは一度ご相談ください。手続きをきちんと済ませておくことで、将来のトラブルやご家族の負担を軽くすることができます。