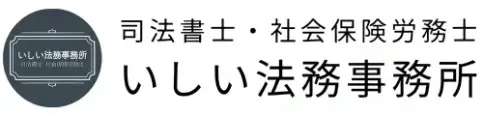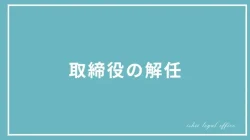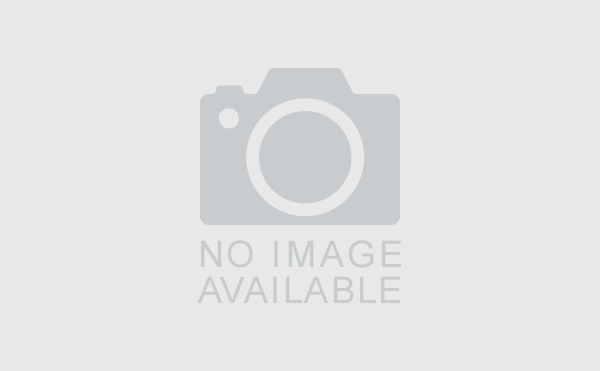就業規則における懲戒処分の基本と運用ポイント
会社(個人事業主を含む)は、従業員の行為が企業の秩序や業務に悪影響を及ぼす場合、その従業員に対して懲戒処分を検討することあります。会社は自由に懲戒処分の決定をすることができるのでしょうか?
この記事では、就業規則における懲戒処分の規定方法や実際に処分を行う際の注意点について細かく解説します。就業規則を作成する際の参考にしてください。
投稿者プロフィール
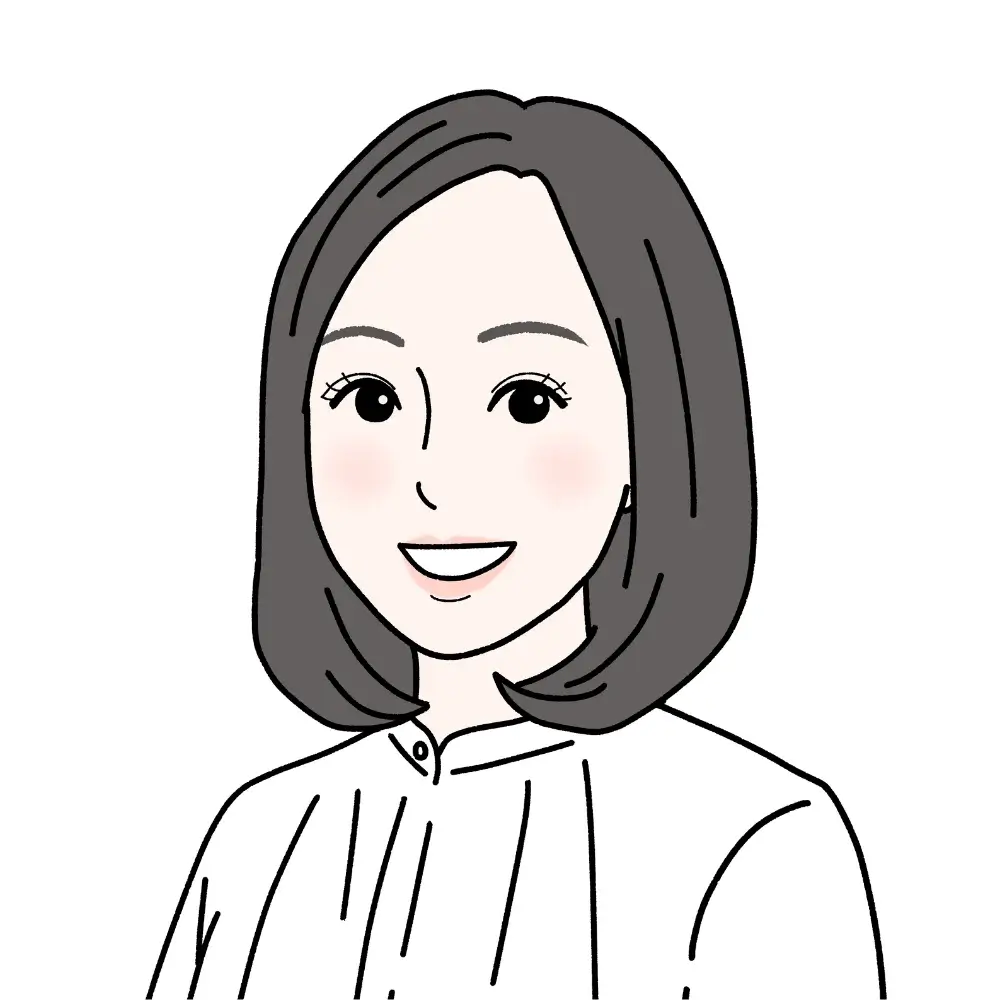
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
懲戒規定の基本
懲戒処分とは?
懲戒処分とは、従業員が就業規則などの社内ルールに違反した場合、会社が従業員に対して実施する懲罰的な処分のことです。
会社が懲戒処分を行うためには、必ずあらかじめ就業規則に懲戒規定を設けておく必要があります。また、懲戒処分は、従業員の権利に直接関わる重要な制度のため、労働基準法をはじめとする労働関連法令に準拠し、公正かつ適切な運用が求められます。
懲戒処分の主な種類
懲戒処分には、一般的に軽いものから戒告、けん責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇があります。これらの懲戒処分は、違反行為の重大性や従業員の過去の違反歴などを総合的に考慮し、過度な懲戒処分にならないよう注意しながら判断する必要があります。
なお、同じ事案について複数回懲戒処分を行うことは認められていません。
懲戒処分の手続き
懲戒処分を実施する際には、公正な手続きを踏まなければなりません。
具体的には、懲戒事由を明確に示し、従業員に対し十分な弁明の機会を与え、事実関係や証拠を慎重に検討した上で、懲戒処分を決定する必要があります。
また、懲戒処分を決定した場合には、その内容を従業員に書面で通知するなどにより、後々トラブルや法的紛争が生じたときに困らないような手続きをとることも大切です。
減給処分時の留意点
減給処分を行う際には、減給の期間や減給される賃金の割合などを明確に定めておかなければなりません。減給の制裁は、労働基準法で厳密な上限が設けられています。
具体的には、減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています(労基法91条)。
なお、出勤停止により働かなかった従業員に対してその期間分の給与を支給しないことについては、この減給の制限は適用されません。なぜなら、働かなければその期間賃金が発生しないのは当然であると考えられるからになります。これを、「ノーワーク・ノーペイの原則」をいいます。
懲戒事由の定め方
懲戒事由の明確化
就業規則で懲戒規定を設ける際は、「どのような行為が懲戒対象となるか」「どんな罰則を受けるか」をできるだけ具体的に示すことが重要です。
たとえば、「正当な理由なく、無許可欠勤をしたとき」など、具体的に行為を明示した条項が望ましいでしょう。
とはいえ、すべてのケースを細かく列挙するのは現実的に困難です。そのため、具体的な事例を挙げつつ、包括的な懲戒事由を定めることも有効です。
包括的な懲戒事由としては、「会社の信用を低下させる行為があったとき」や「その他就業規則に違反し、企業秩序に悪影響を発生させたとき」などが挙げられます。
懲戒事由を明記する重要性
実際に懲戒処分を実施する際、従業員自身が「自分の行為がどの懲戒事由に該当するのか」を理解できるよう、根拠となる条項を明示するようにしましょう。
もし、懲戒事由が曖昧なまま懲戒処分を行えば、従業員と後を引くトラブルに発展するリスクが高まります。
懲戒手続きを行う際の注意点
懲戒の有効性について
懲戒処分は、該当する従業員の行為の内容や経緯、その他の状況に照らして「客観的に妥当で、社会常識の範囲内かどうか」が問われます。懲戒処分が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされています(労働契約法15条、16条)。
したがって、就業規則に懲戒事由が定められていても、必ずしもその通りに処分が有効になるわけではありません。懲戒事由と処分内容のバランスを慎重に見極める必要があります。
弁明の機会を与えること
懲戒処分を行う際には、従業員の権利を尊重し、公正な手続きを踏まなければなりません。
懲戒処分の前には、必ず従業員に対し「懲戒事由」となる行為を明示し、本人に弁明の機会を与え、証拠を十分に検討した上で、懲戒処分を決定しましょう。
従業員に弁明の機会を与えるときは、その従業員が充分に弁明できるよう、適切な時間と機会を与える必要があります。特に重い処分を検討する場合は、複数回のヒアリングを行うなど、十分に意見を聞く配慮も重要です。
また、弁明の機会を設ける際には、プライバシーの確保を維持しつつ、従業員の心身に過度な負担がかからないよう環境面にも配慮しましょう。
懲戒処分の適切な通知と運用
懲戒処分を決定した際は、従業員への通知は、書面で行うようにしましょう。通知書には、懲戒理由、懲戒処分の内容、処分の日付などを明記します。
また、通知書は、従業員に直接手渡すなど、確実に受け取れる方法で送付し、可能であればサインや受領記録も残しておくと後のトラブル防止につながります。
懲戒処分は、あくまでも最終手段です。懲戒処分を行う前に、従業員に対して、指導や教育を行い、改善を促すことが重要です。処分が必要となった際も従業員の人権やプライバシーを配慮した運用を徹底しましょう。
まとめ
就業規則における懲戒処分の規定は、会社にとって従業員の規律維持や秩序の確保、会社の信用を守る上で重要ですが、従業員の権利を制限する可能性があるため、その内容や運用方法は十分に慎重を期す必要があります。
懲戒処分を行う際には、従業員に弁明の機会を与えるなど、公正な手続きを踏むことが重要です。当事務所は、就業規則の作成や見直しのご相談も承っております。新しく就業規則を作りたい方、ネット情報で作った就業規則をチェックして欲しいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。