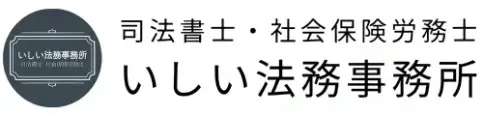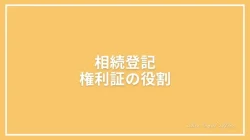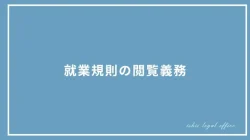数次相続の場合の相続登記の一括申請|中間省略登記
数次相続が発生した場合、相続登記の手続きは複雑になりがちです。しかし、要件を満たせば一括申請(中間省略登記)が可能となり、手間を大幅に削減できます。この記事では、数次相続登記の一括申請(中間省略登記)について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール
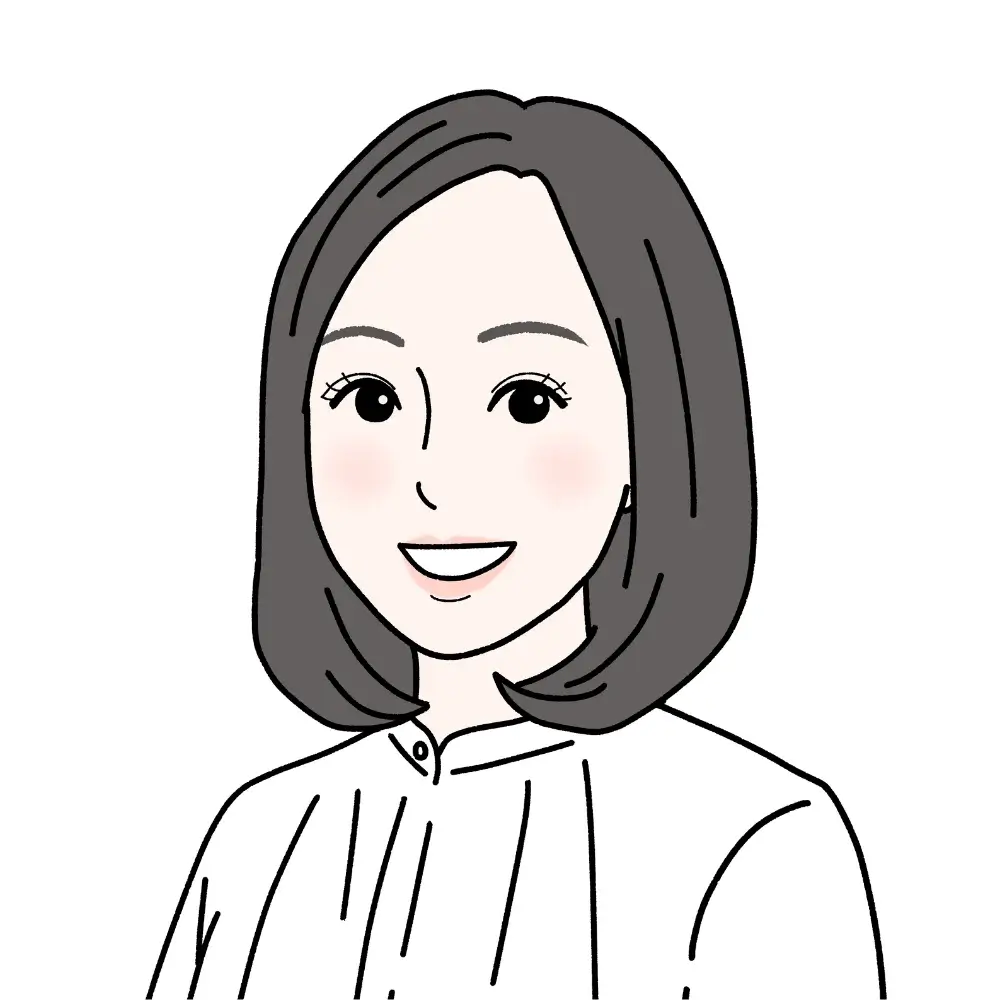
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
数次相続とは?一括申請(中間省略登記)の基本
数次相続の定義と具体例
数次相続とは、相続が発生した後に、その相続人が遺産分割協議を終える前に亡くなってしまい、さらに相続が発生することを指します。これは、最初の相続(一次相続)が発生した後、遺産分割が完了する前に、一次相続の相続人が亡くなってしまうことで、その相続人の相続(二次相続)が生じている状況となります。
例えば、祖父が亡くなり、父が相続するはずだったが、父が遺産分割前に亡くなり、子が相続人となるケースです。この場合、祖父から父への相続(一次相続)と、父から子への相続(二次相続)が連続して発生しています。このようなケースでは、数次相続として、一連の手続きを行わなければなりません。数次相続が発生すると、相続関係が複雑になり、手続きも煩雑になる傾向があります。
一括申請(中間省略登記)が可能なケースと条件
二次相続が生じたときの相続登記は、2回の相続登記申請をすることが原則です。しかし、一定の要件を満たせば、相続登記の一括申請(中間省略登記)が可能です。一括申請(中間省略登記)は、手続きを効率化し、費用を節約することにもつながります。
一括申請(中間省略登記)の要件は、一次相続で不動産を取得する者が一人の場合です。一番簡単な例を紹介します。不動産の所有者であるAが亡くなりました。Aの相続人はBのみです。Bは、AからBへの相続登記をする前に亡くなってしまいました。Bの相続人はCのみだったとします。原則的な手続きは、AからBへの相続登記の後、BからCへの相続登記をすることになります。しかし、このケースでは、一次相続による不動産の取得者(中間の相続人)はBの一人のみとなりますので、AからCへの一括申請(中間省略登記)が可能となります。
上記の例は、一次相続の相続人が一人の場合でしたが、一次相続の相続人が複数でも、遺産分割や相続放棄などにより、一次相続により不動産を取得する者が一人であれば一括申請(中間省略登記)が可能です。また、二次相続による不動産の取得者は、複数人でも構いません。
連続して数次相続が生じた場合
数次相続が連続的に生じ、二次相続の後に三次相続が生じた場合でも、一次相続と二次相続による不動産の取得者がそれぞれ一人のときは、一括申請(中間省略登記)ができます。
一次相続から三次相続まで含めた相続人全員の協議で、三次相続の相続人が不動産を取得することとなったとします。この場合でも、一次相続から三次相続まで含めた相続人全員による遺産分割協議書を作成し、三次相続の相続人へ、直接相続登記申請ができることとなっています(平成29年3月30日民二第237号)。
数次相続登記における注意点
まずは、相続人を正確に把握することが重要です。特に、数次相続の場合、相続人が多数にわたる可能性があります。相続人の確定は、戸籍謄本や除籍謄本を調査することで行います。相続人が確定したら、相続人全員に連絡を取り、相続人間の話し合いで遺産の取得者を決め、その合意の内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないため、最初に相続人の把握が正確にできていないと、もう一度話し合いをしなければならなくなります。そのため、相続人の確定は、数次相続の重要な最初のステップであり、丁寧に行わなければなりません。
まとめ
数次相続登記は複雑で専門的な知識が求められる手続きの一つでもあります。一括申請(中間省略登記)を利用することで効率化できますが、必要な書類を漏れなく収集し、正確に把握しなければなりません。
当事務所は、相続に関する相談を承っております。オンラインの相談もお受けしています。お気軽にご連絡ください。