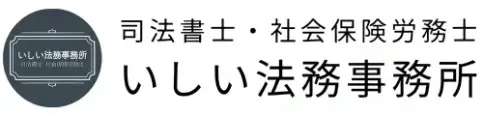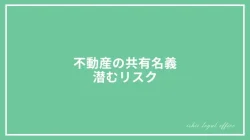相続手続きの期限とは?期限内にやるべきことを解説
相続は人生の中で何度も経験するものではなく、準備もなく急にその時が訪れることがほとんどです。加えて、期限がある手続きや専門的な知識が必要なものも多く、不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、特に「不動産のある相続」に焦点を当てて、相続手続きの全体像とポイントをわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール
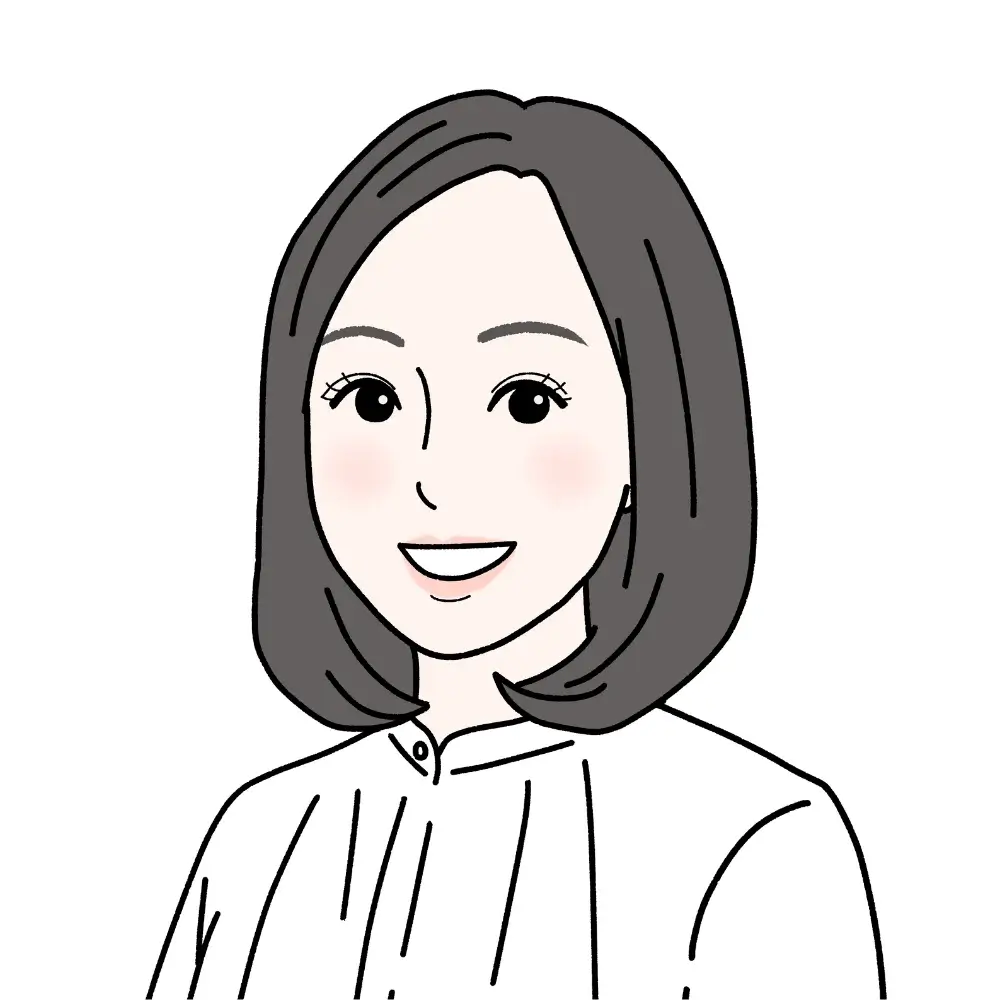
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
相続手続きの全体像と流れ
相続に関する手続きは、おおまかに次の5段階で進みます。
- 死亡届の提出と葬儀
まずは市区町村役場に死亡届を提出します。戸籍に死亡の事実が記載されることで、相続の諸手続きがスタートできるようになります。 - 法定相続人の確定と遺言書の確認
戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定します。同時に遺言書が残されているかを調べます。公正証書遺言はすぐ使用できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必須です。 - 遺産(プラス・マイナス)の調査
被相続人名義の財産と負債を一覧化します。不動産、預貯金、有価証券、保険、借入金などを漏れなく把握することが重要です。 - 相続放棄や遺産分割の判断
相続を放棄したいときは、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。放棄しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い「誰が何を引き継ぐか」を決定します。 - 名義変更などの実務手続き
協議の内容がまとまったら次のような名義変更や手続きを行います。- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預金の解約・払戻し
- 自動車や株式の名義変更
- 相続税の申告など
相続手続きの最初のステップ
死亡診断書の受取と死亡届の提出
死亡診断書(または死体検案書)は医師が死亡日時・原因を証明する書類で、故人が亡くなった病院・診療所で交付されます。死亡届はこの診断書と1枚になっており、死亡の事実を知った日から7日以内(海外で死亡の場合は3か月以内)に、死亡地・本籍地・届出人のいずれかの市区町村役場に提出します(戸籍法86条)。
死亡届を提出することで、故人の戸籍が除籍され、相続手続きを進めることができます。
火葬許可証
亡くなった方のご遺体を火葬するためには、火葬許可証が必要です。許可証は、市役所や町村役場で発行されます。許可証は、死亡届提出時に同時発行されるケースと、別途申請が必要な自治体があります。
この火葬許可証(埋葬許可証)は、後に納骨時にも使うため、大切に保管しましょう。
世帯主の変更届
世帯主が亡くなった場合、14日以内に世帯主変更届を出す義務があります(住民基本台帳法25条)。ただし、世帯員が1人なるときなど、自治体によっては不要となる場合もあります。
公的年金と健康保険の手続き
公的年金
年金受給者が亡くなられた場合は、14日以内に年金受給権者死亡届の提出が必要です。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を登録している方は、原則として、省略できる取り扱いとなっています。
また、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金または亡くなった日より後に振込みされた年金のうち亡くなった月までの年金、いわゆる未支給年金はその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金は2ヵ月毎の後払いなので、必ず未支給年金が発生することになります。
未支給年金は、受け取った方の所得税の対象となる一時所得に該当します。
提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。条件次第では遺族年金などを受給できるので確認しましょう。
国民健康保険、後期高齢者医療保険
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、資格喪失届を市区町村に提出します。勤務先の健康保険加入者については事業主が手続きを行います。
葬祭を行った人は葬祭費(会社の健康保険に加入していた人は埋葬料)の支給を受けられます。葬儀の翌日から2年以内に申請が必要で、支給額は保険者ごとに異なります。
相続放棄と限定承認の申出
相続放棄や限定承認をする場合は、原則、自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内にしないといけません。
相続放棄や限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にします。
相続(単純承認)とは、相続によって財産だけでなく、負債も無限に引き継ぐことをいいます(民法920条)。
一方、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。このため、もし財産よりも負債が多い場合は、相続放棄をすることで借金の支払い義務からも免れることが可能です。
限定承認とは、相続によって得た財産額までの範囲でのみ、被相続人の債務や遺贈の責任を負う制度です。限定承認は相続人全員が一緒に申し立てる必要があります(民法923条)。また、手続き後5日以内にすべての相続債権者と受遺者に対し、限定承認をした旨と一定期間内に債権申出をするよう官報で公告し、個別にも催告することが義務付けられています(民法927条)。
準確定申告と相続税について
準確定申告
被相続人が生前に受け取った収入について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
準確定申告は、被相続人が亡くなった後、被相続人の収入についての所得税を支払うための申告です。
準確定申告は、相続人が被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出して行います。
相続人が2人以上いる場合は、原則、連署により提出します。
相続税の申告と納付
相続税は、相続によって取得した財産について相続人に対して課せられる税金です。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。期限を過ぎて税金を納めると延滞税が発生する場合があります。
相続税の申告は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。
相続登記やその他の手続き
遺留分侵害額請求について
兄弟姉妹以外の法定相続人で、法律で認められている遺留分が遺言などによって侵害されている場合、遺留分侵害額請求が可能です。遺留分権利者は、知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しないと権利が消滅します(民法1048条)。
遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続分です。遺言によって遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことで、他の相続人へ金銭請求をすることができます。
相続登記の手続き
相続登記とは、不動産の所有者の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。例えば、遺言や遺産分割協議で決まった人がその不動産の新しい所有者となります。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の所在地を管轄する法務局で申請しなければなりません。
相続登記が完了しなければ、不動産の売却等もできませんので注意が必要です。
また、相続人間で協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」という新しい簡易な登記制度も利用できます
死亡保険金の請求と預貯金の解約
亡くなった方の生命保険金は、契約書にもとづいて保険会社に申請することで受取が可能です。また、預貯金や有価証券の解約も、遺言や遺産分割協議の内容に従って、それぞれ手続きを行います。
相続手続きを円滑に進めるためのポイント
遺言書の有無を確認する
遺言書の有無で手続きの内容が変わりますので、相続開始後、速やかに確認することが重要です。
自筆証書遺言は、被相続人の家や貸金庫などを探します。自筆証書遺言を発見した相続人又は遺言書の保管者は、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。
ただし、新たに、法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが開始されているので、法務局に照会して確認する必要もあるでしょう。
法務局で保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認の必要はありません。
公正証書遺言を被相続人が作成していた場合は、公証役場で検索が可能なので、最寄りの公証役場で確認しましょう。なお、公正証書遺言も遺言書の検認手続きは不要です。
相続人の調査と相続財産の調査
相続財産を、法定相続人のうち誰が何を相続するのか話し合う必要があります。
場合によっては、相続放棄を検討することもあるかもしれません。
そのためには、まずは法定相続人の調査と、相続財産と債務の特定をしないといけません。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全てを取得し、調査していくことになります。
不動産や預貯金口座が多い場合は、法定相相続証明情報の制度(被相続人の相続関係を一覧にし、その一覧図を発行する制度)を利用すると手続きがスムーズになるので検討してもいいかもしれません。
被相続人が本籍地を何度も転籍している、代襲相続や数次相続が発生していて相続人がたくさんいるときなど、個人で取得するのが大変な場合は司法書士などの専門家に依頼することも一つの方法です。
遺産分割協議
法定相続人全員で相続財産をどのように分けるか遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
まとまった遺産分割協議に沿って被相続人の相続財産をそれぞれ取得する相続人に分ける手続きと相続税の申告を行います
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる方法もあります。
専門家への相談とタスク管理
相続手続きは煩雑で期限も厳守が求められます。不安がある場合は専門家に相談するのも一つの選択肢です。
相続手続きは、たくさんの知識が必要となるため、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
各種手続きの期限を洗い出し、スケジュール通りに進行するためのタイムラインを作成します。
タイムラインを作成することで、各手続きの期限を把握し、スケジュール通りに手続きを進めることができます。
タイムラインには、期限だけでなく、必要な書類や手続きに必要な期間なども記載しておくと便利です。
まとめ
相続手続きにはたくさんの期限があります。期限を把握していないと、予想もしない不利益が生じる可能性があります。
亡くなられた方の意思を尊重し、遺族が安心して生活できるよう、相続手続きの期限を把握、適切な時期に手続きを進めましょう。