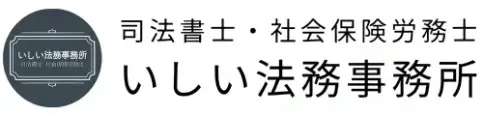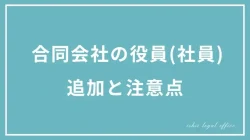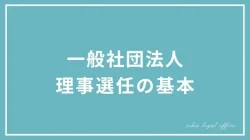就業規則の作成によるメリットとは?企業経営に欠かせない基本ルールの重要性
就業規則とは、会社と従業員の間で守るべきルールを明文化した文書であり、組織運営の“基本ルールブック”ともいえる存在です。労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に就業規則の作成と届出が義務付けられていますが、10人未満の事業所であっても、就業規則を整備することには大きなメリットがあります。
本記事では、就業規則を作成する意義やメリットを解説しながら、企業が円滑な運営を行うために知っておきたいポイントをご紹介します。
投稿者プロフィール
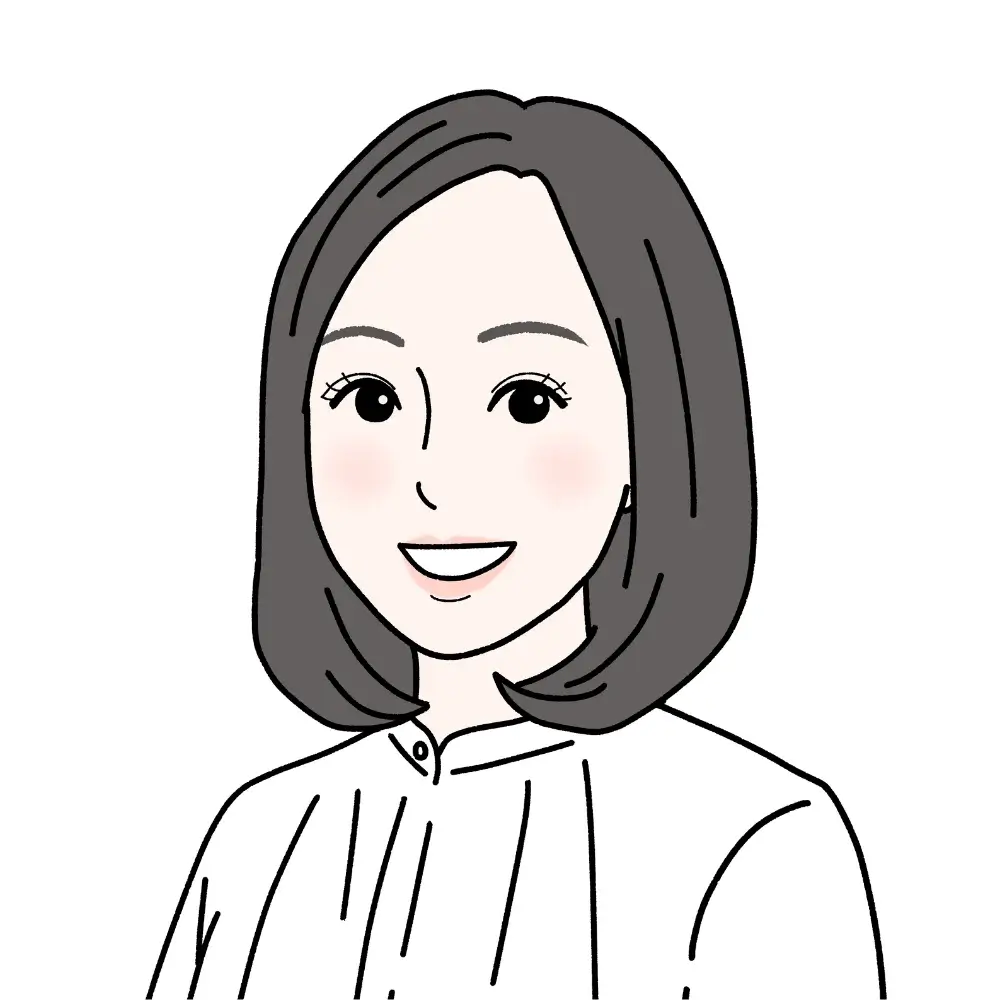
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
就業規則の役割
労使関係の安定とトラブル予防
就業規則の主な役割は、労働条件の明確化と労使トラブルの予防です。労働時間、休日、賃金、退職、解雇など、従業員にとって重要な事項を就業規則に明記することで、双方の認識のずれを防ぎ、安心して働ける職場環境を構築できます。
特に、法的根拠のない曖昧なルール運用は、後に労働トラブルの火種となることがあるため、実態に即した規定を明文化しておくことが重要です。
なお、インターネット上の雛形をそのまま使うのは危険です。業種や組織規模、職場環境に応じて内容をカスタマイズしなければ、かえって誤解やトラブルを招く恐れがあります。
また、就業規則は労働条件だけでなく、業務の流れや社内ルールを明文化したマニュアル的要素を持たせることも可能です。労務管理の基盤となる文書として、多面的な活用が期待できます。
労働契約との関係|就業規則が基準となる仕組み
就業規則は、社内における統一的なルールとして機能し、個々の労働契約書の基準となる役割を持ちます。以下のように、規範性の順序がある点も理解しておくべきです。
労働関係法令 > 就業規則 > 個別の労働契約
つまり、個別契約で就業規則に反する内容を記載しても、原則として就業規則が優先されます。もちろん、就業規則は事業主側も遵守すべきルールとなります。
さらに、パートやアルバイトなど、非正規社員向けの就業規則を別途設けている場合は、「同一労働同一賃金」の観点からも整合性を確認することが求められます。全体として矛盾のないルール設計を意識しましょう。
年次有給休暇の基本と就業規則|斉一的取扱いから退職時の取扱いまでについては
懲戒規定を設ける重要性|トラブル対応の備え
従業員が就業規則に違反した場合の処分(遅刻・無断欠勤・ハラスメントなど)については、あらかじめ懲戒規定を明記しておく必要があります。何を違反行為とし、どのような処分を科すかを明確にすることで、処分時のトラブルを防止できます。
ただし、記載されていない処分は原則として実行できません。また、懲戒は「社会通念上相当」と認められる範囲でなければ無効となる可能性があります。合理性のある規定と適正な運用が重要です。
就業規則の作成手順
就業規則の作成義務|10人未満でも整備をおすすめ
常時10人以上の労働者を雇用する事業主には、就業規則の作成と届出義務があります。ここでいう労働者には、パートタイマーやアルバイトなど短時間勤務の従業員も含まれます。
人数のカウントは事業所単位で行われるため、複数拠点があっても、それぞれの事業所で10人未満なら義務はありません。ただし、義務の有無にかかわらず、就業規則を整備しておくことには大きな経営的メリットがあります。
就業規則の作成と記載事項の確認
就業規則を新たに作成する場合や内容を変更する場合には、労働者の過半数代表者または労働組合の意見を聴く必要があります(労働基準法第90条)。この「意見聴取」は「同意取得」までは求められませんが、スムーズな運用のためには、従業員の理解と協力を得ることが望ましいです。
また、就業規則には、法令により記載が義務付けられている項目(絶対的記載事項)や、定める場合には記載が必要な項目(相対的記載事項)があります。必要な内容に漏れがないよう、丁寧に確認しながら作成することが重要です。
就業規則の周知義務
作成・変更した就業規則は、従業員に周知する義務があります。この周知を怠ると罰則の対象となります。
周知の方法としては以下が認められています。
- 書面で配布する
- 事務所に備え付ける
- パソコンや社内ネットワークで常時閲覧可能にする
周知義務を怠ると罰則が科される可能性もあるため、確実な対応が求められます。
労働基準監督署への届出
作成義務のある事業所は、就業規則を作成・変更した場合、遅滞なく労働基準監督署へ届出を行う必要があります。賃金規程やパートタイム労働者向けの規程などを別に設けている場合、それらも就業規則の一部として届出の対象となります。
届出の際には、労働者代表の意見書の添付が必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。
なお、違反した者は、30万円以下の罰金が科せられることとなっています(労基法120条)。
不利益変更について
就業規則は、一度作成したら終わりではなく、法改正や会社の実情に応じて定期的な見直しが必要です。その際、内容を変更した結果、労働者にとって不利益となる場合は注意が必要です。
原則として、労働者の同意なく労働条件を不利益に変更することはできません(労働契約法第9条)。ただし、業務運営上やむを得ず合理性が認められる場合には、例外的に変更が可能です。
トラブルを避けるためにも、不利益変更が疑われる場合には、労働者への丁寧な説明と合意取得(書面化)を検討しましょう。
まとめ
就業規則は、企業と従業員の信頼関係を築くための土台であり、労使トラブルを未然に防ぐ重要なツールです。法令を踏まえた適切な内容と手続きをもって作成・見直しを行うことで、安心・安定した職場環境が実現します。
当事務所では、事業所ごとの実情に即した就業規則の作成・改定・届出までをワンストップでサポートしております。初めての方もお気軽にご相談ください。