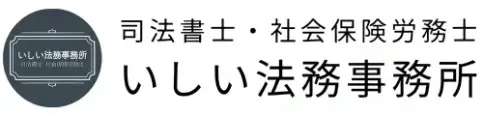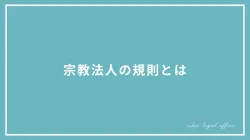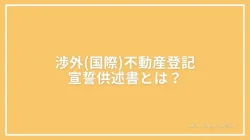渉外相続登記とその添付書類の基本
渉外相続登記は、日本の不動産の登記名義人に相続が発生したときに、国際的な要素が含まれる登記のことをいいます。通常よりも複雑な手続きとなります。本記事では、渉外相続登記と必要書類の基本についてわかりやすく解説します。管轄法務局への確認は不可欠ですが、少しでも参考になれば幸いです。
投稿者プロフィール
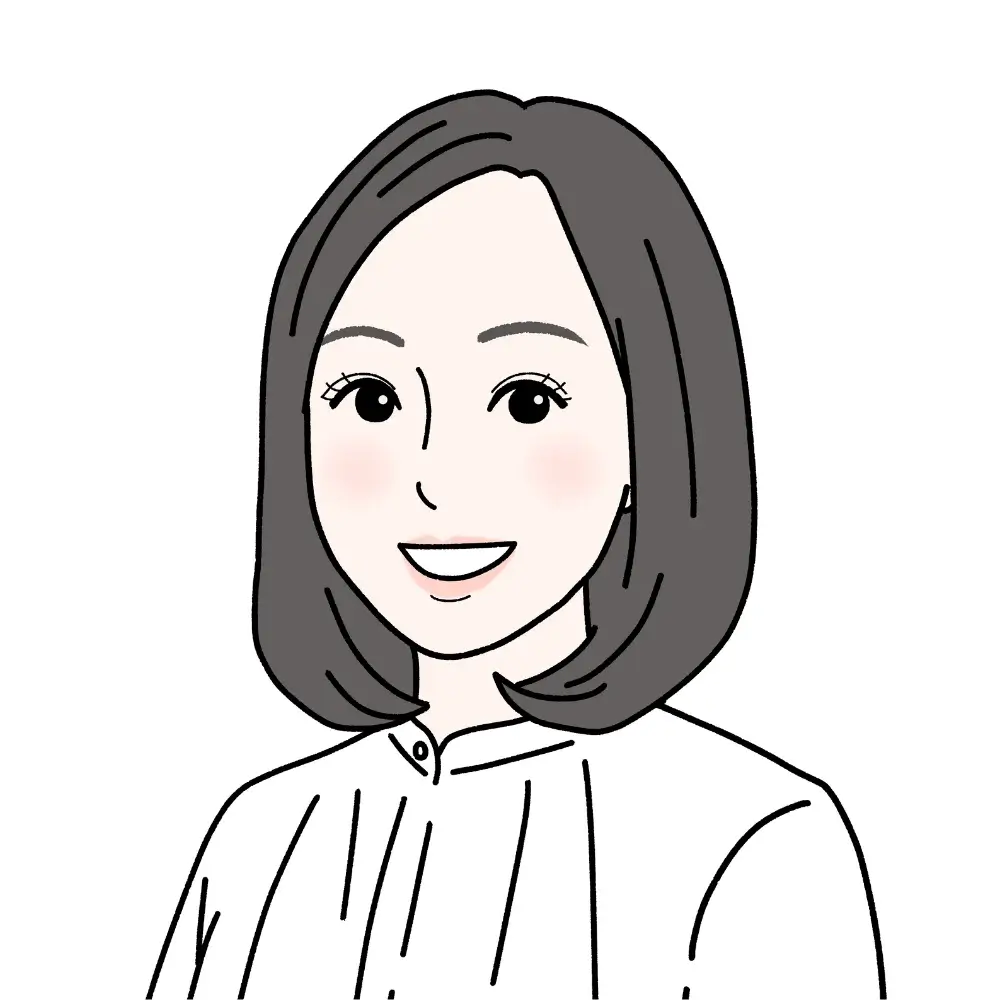
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
渉外登記とは?基本と重要なポイント
「渉外」の読み方と意味
まず、「渉外(しょうがい)」とは、一般的に次の2つの意味で使われます。
①外部と連絡・交渉すること
②ある法律事項が、国内だけでなく外国にも関係すること
相続や不動産登記においての「渉外」は、主に後者の意味で使われます。
つまり、渉外登記とは、相続人や被相続人、名義人が外国籍である、または国外に居住しているといった、国際的な要素を含む登記を指します。
渉外相続登記とは、渉外登記のなかでも、相続を原因とする不動産登記のことをいいます。渉外相続登記は、通常の相続登記とは異なり、国籍・居住地・書類の発行国などの「国際的要素」が関係するため、手続きが複雑になる傾向があります。
たとえば、次のようなケースが該当します。
- 相続人の一人がアメリカに居住している
- 被相続人が外国籍だった
- 相続人が日本国籍だが、長年海外に在住している
- 外国で作成された相続関係の証明書を利用する必要がある
こうした場合には、通常の相続登記とは異なる添付書類や注意点が生じます。
通常の登記との違い|渉外登記の特徴
渉外相続登記では、以下の点で通常の相続登記と大きく異なります。
必要書類の違い
通常の登記では、日本国内で発行された書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)を使用しますが、渉外登記では外国で発行された書類(例:死亡証明書、宣誓供述書など)が必要になることがあります。
これらの外国文書は、原則として日本語に翻訳し、その翻訳文を登記申請書類に添付しなければなりません。
海外在住者の連絡先の提供
また、海外居住者が登記名義人となるときは、国内における連絡先となる者の情報を提供しなければなりません。このように、渉外登記のときは、通常よりも複雑になります。
渉外相続登記に必要な書類
渉外相続登記における「準拠法」の確認が第一歩
渉外相続登記を進めるにあたり、被相続人が(亡くなられた方)が外国籍の場合は、まずは準拠法の決定をしなければなりません。
日本の国際私法に基づき、被相続人の本国法が相続に適用されるのが原則とされているため、どの国の法律が相続に適用されるのかを明確にすることが、渉外相続登記の出発点となります。
準拠法の違いによって、必要となる書類の種類や有効性の判断が変わるため、最初の段階での確認が重要です。
渉外相続登記に必要な添付書類の種類と取得方法
渉外相続登記で必要となる書類は、ケースごとに異なりますが、主に次の3つのカテゴリーに分けられます。
- 相続を証する書類
- 住所を証する書類
- 印鑑証明書に代わる書類
なお、渉外相続登記に必要な書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付しなければなりません。翻訳者の資格は問われませんが、翻訳者名を記載する必要があります。
相続を証する書面|被相続人の死亡と相続関係を証明
被相続人が亡くなった事実、相続人との関係性を証明するための書類です。
通常、以下のような書類を用意します。
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 死亡証明書
- 宣誓供述書
住所を証する書面|登記名義人の現住所を確認
登記名義人となる相続人の住所を証明するため、以下の書類が使用されます。
- 住民票(日本の在留期間が3か月を超える外国籍の人)
- 在留証明書(在外邦人の場合)
- 宣誓供述書(国籍も住所も日本にない場合は、旅券のコピーも必要)
「在外邦人」とは、海外に居住している日本国籍の方を指します。
印鑑証明書に代わる書面|署名の真正性を証明
相続登記では、遺産分割協議書などの重要書類に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。日本の印鑑証明書は15歳以上で日本に住民票がある場合のみ登録ができることとなっています。
そのため、日本に住民票がない場合は、印鑑の登録ができません。そこで、実印を押印する代わりに署名をし、その署名が本人のものであることを証する必要があります。
- 署名証明書(在外邦人の場合)
- 宣誓供述書
いずれも、署名が本人によるものであることを証明するために重要な書類です。
スムーズな手続きのためのポイントと注意点
渉外相続登記は、通常の相続登記に比べて複雑で専門的な知識が求められます。専門家への相談は時間と費用がかかる場合がありますが、状況によっては専門家への依頼を検討しましょう。
渉外相続登記は、通常の相続登記に比べて、必要書類の収集、翻訳などに時間がかかるため、手続きに時間がかかる傾向があります。渉外相続登記の手続きを進める際には、時間的余裕を持って準備しましょう。
まとめ
渉外相続登記は、国際的な事情が絡むため、通常の相続登記と比べて手続きが複雑になります。準拠法の決定、必要書類の収集、翻訳などの様々な手続きが必要となり、時間と労力がかかることもあります。
個別のケースによって必要書類が異なるため、不明点がある場合は、必ず事前に法務局または専門家に相談するようにしましょう。