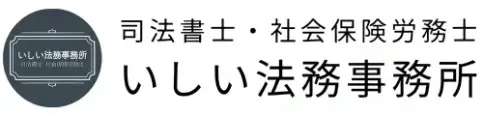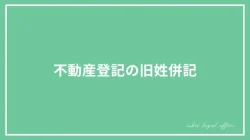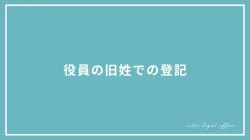相続人が一人のときの遺産分割協議書|数次相続の場合の不動産登記と注意点
数次相続が発生し、最終的な相続人が一人の場合、不動産登記はどう進めればいいのでしょうか?数次相続とは、相続が発生した後に、相続人の内の一人が亡くなり、さらに相続が発生した状態のことをいいます。数次相続が発生し、最終的な相続人が一人のときでも遺産分割協議書の作成が必要なときがあります。本記事では、数次相続において遺産分割協議書が必要な場合と、その場合の遺産分割協議書の書き方を解説します。
投稿者プロフィール
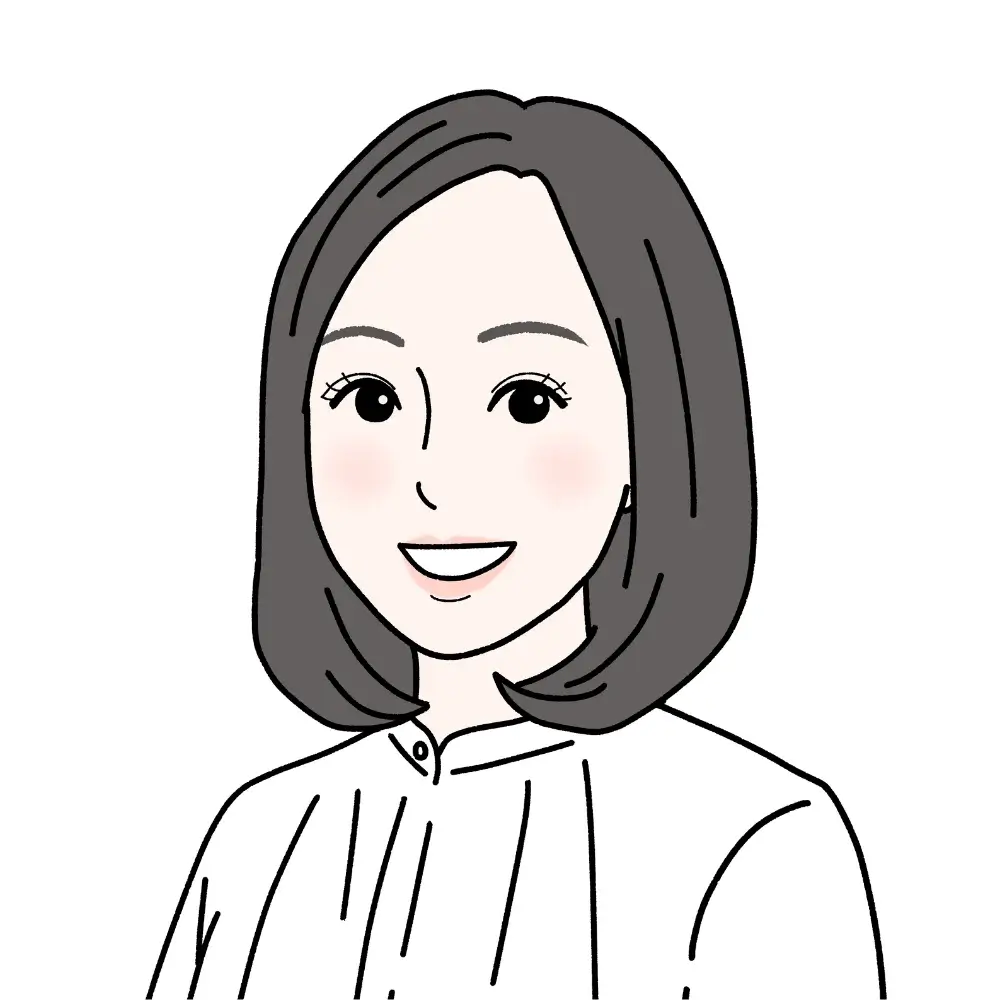
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
数次相続とは?基本知識とポイントを解説
数次相続とは、一度相続が発生した後に、その相続手続きが完了する前にさらに相続人が亡くなり、連続して相続が発生したケースのことをいいます。
たとえば、祖父が亡くなり、その遺産を相続するはずだった父が、手続きの途中で亡くなった場合を想像してください。この場合、父が相続する予定だった遺産分(祖父の遺産)は、父の相続人(たとえば子ども)が引き継ぐことになります。
数次相続が起こると、相続関係が複雑になりやすく、相続人や手続きの範囲を正確に把握することが求められます。
相続人が一人のケースと遺産分割協議書の考え方
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を合意した内容をまとめる書類です。不動産を相続する人を特定したり、預貯金の分配方法を定めたりします。
ただし、相続人が最初からひとりしかいない場合、そもそも分割の余地がないため、遺産分割協議書は原則不要です。分け合う相手が存在しないので、協議自体が成立しません。
数次相続で相続人が一人の場合の遺産分割協議
複数の相続が重なる数次相続の場合でも、最終的に相続人が一人になったら、遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)を作成するかどうかは状況によって異なります。
Bの生前に遺産分割協議をしていなかった場合
たとえば、Aが亡くなり、Aの相続人がBとC。その後、Aの遺産分割協議が終わる前にBが死亡。Bの相続人はCだけ、というケースを考えます。
この場合、Bが生前にAの遺産について協議をしていなければ、遺産分割協議書は不要です。これは、Aの遺産は、Aの相続開始時において、BとCがAの遺産を共有し、その後、Bの相続開始時において、その全てがCに帰属したと考えられているからです(東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件)。
不動産登記手続きにおいては、A名義の不動産について、法定相続分の割合でBとC名義で相続登記をします。その後に、B名義の不動産についてCへ相続登記をすることになります。
Bの生前に遺産分割協議をしていた場合
一方、BとCが生前にすでにAの遺産について遺産分割協議をしていた場合、その内容(例えば「Aの不動産はCが相続する」など)の遺産分割協議証明書を作成します。
このときの不動産登記は、遺産分割協議証明書を添付して、A名義の不動産を直接C名義に相続登記をします(平成28年3月2日付法務省民二第154号)。
遺産分割協議書の作成ポイント
基本的な記載項目
遺産分割協議書には、被相続人(亡くなった方)の特定情報を必ず記載します。
具体的には被相続人の氏名、最後の本籍、最後の住所、死亡年月日や生年月日を記載します。
これらの情報を正確に書いたうえで、遺産分割に関する合意内容や取得する財産、各相続人の氏名・住所も記入します。そして、相続人全員が実印で押印するのが一般的です。
数次相続で相続人が一人の場合の遺産分割協議証明書
もし数次相続の結果、最終的な相続人が一人だけとなった場合は、前述ケース(Bの生前にBとCでAの遺産分割協議をしていた)では、当時の協議内容およびその日付を「遺産分割協議証明書」に明記します。なお、協議日はBの生前である必要があります。
しかし、既にBが亡くなっている以上、Bの署名・押印はできません。そのため、Cが、「Aの相続人の一人、かつBの唯一の相続人」として協議証明書に署名し、実印を押す形になります。
まとめ
数次相続のケースは手続きや書類作成が複雑になりやすいものです。
相続・遺産分割でお困りの際は、専門家によるサポートを活用することで、安心して手続きを進められます。
当事務所では相続手続きのサポートも承っています。ご不明な点、ご相談がありましたらどうぞお気軽にご連絡ください。