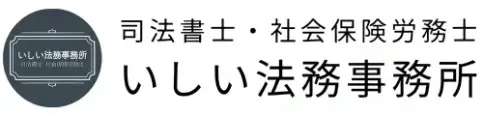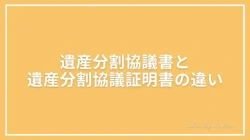年次有給休暇の基本と就業規則|斉一的取扱いから退職時の取扱いまで
就業規則における年次有給休暇の規定は、企業の法令遵守だけでなく、労働者のワークライフバランスや離職率低下の面からも大切です。
この記事では、有給休暇に関する規定と管理を複雑にさせない斉一的取扱いについて解説します。
投稿者プロフィール
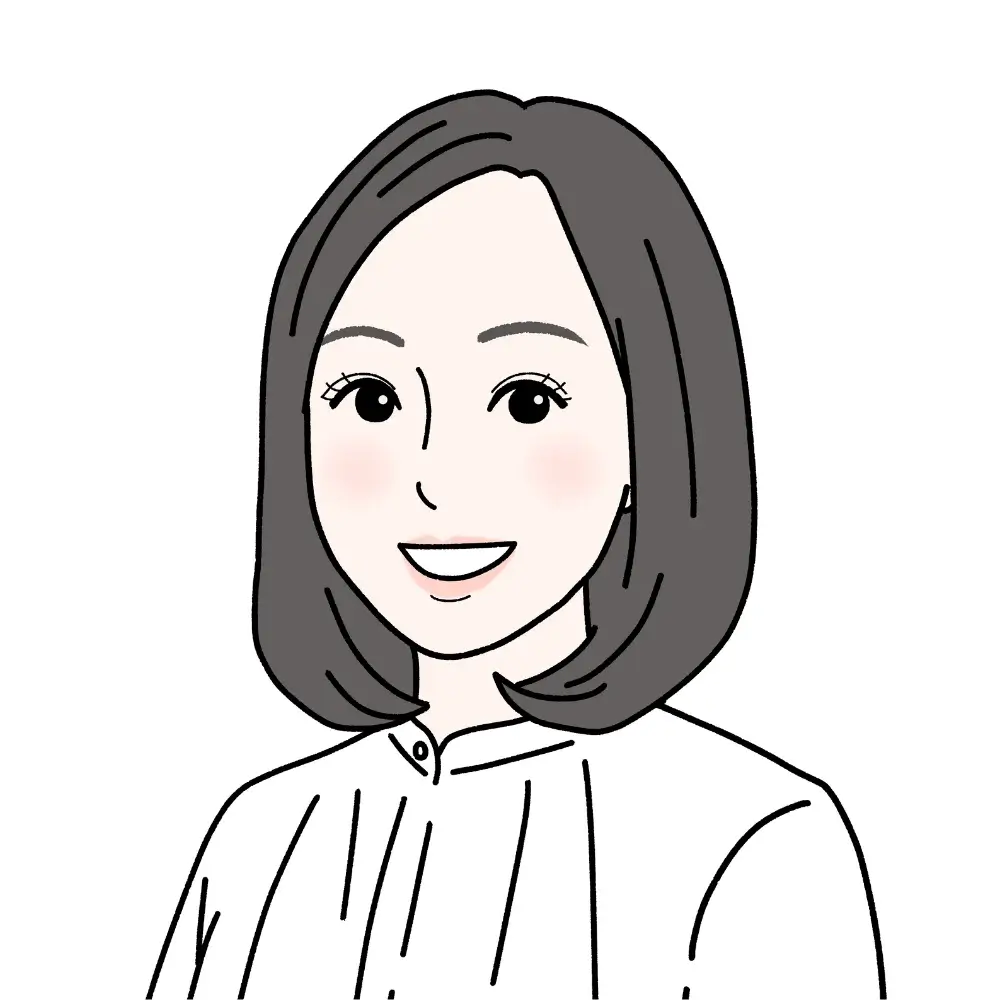
初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
年次有給休暇とは
制度と就業規則への規定
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利で、心身のリフレッシュや私的な用事を済ませる等理由を問わずに取得できる休暇です。
休暇に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項とされていますので、年次有給休暇に関する規定も記載する必要があります。
就業規則に年次有給休暇の規定を記載することは、労働者が安心して年次有給休暇を取得できるためのルールの明確化にもつながり、労使間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な職場環境を維持することが可能になります。
年次有給休暇に関する基本的な考え方
年次有給休暇に関する規定には、付与される基準日、付与条件、付与日数を必ず定める必要があります。
基準日
年次有給休暇の基準日は、労働基準法上は、入社日から6カ月後に最初の年次有給休暇が付与され、その後、1年毎に付与されることとなっています。
もちろん、パートタイム労働者であっても、年次有給休暇が付与されます。
付与条件
付与の条件となる出勤率(8割以上出勤したかどうか)は、期間中の出勤日数を所定労働日数で割ることにより算定します。
分母の所定労働日数には、次のものが除外すべき日とされています(通達)。
①不可抗力による休業日
②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
③正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
④代替休暇を取得した日
また、分母の所定労働日数に入れたうえで分子の出勤日数に含むものとみなすべき日として、次のものがあります。
①業務上の傷病による療養のために休業した期間(法令)
②産前産後の休業期間、育児休業・介護休業を取得した期間(法令)
③年次有給休暇を取得した日(通達)
④その他従業員の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日(通達)
付与日数
正社員の場合
| 基準日 | 入社日 から6 か月後 の日 | 入社日 から1 年6か 月後の 日 | 入社日 から2 年6か 月後の 日 | 入社日 から3 年6か 月後の 日 | 入社日 から4 年6か 月後の 日 | 入社日 から5 年6か 月後の 日 | 入社日から 6年6か月 後の日及び その後1年 ごとの日 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイマーの場合
| 週所定 労働日数 | 1年間の所定 労働日数 | 雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年) | ||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
斉一的取扱い
原則的な基準日に年次有給休暇を付与する場合、労働者ごとに年次有給休暇の基準日が異なることになります。そのため、管理が複雑になってしまいます。
そのような事態を避ける方法が斉一的取扱いにになります。
斉一的取扱いとは、労働者全員の基準日を同一にすることです。
斉一的取扱いが認められる要件は、
①斉一的取扱いにより法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること
②次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること
以上の2つの要件を満たす必要があります。
なお、基準日の回数に制限はなく、年1回(例えば4月1日)でも、年2回(例えば10月1日と4月1日)、またはそれ以上でもかまいません。
退職時の年次有給休暇の取扱い
年次有給休暇は、原則買い取ることはできません。
しかし、労働者が退職するときで、退職時までに年次有給休暇を消化できない場合、消化できなかった年次有給休暇分を事業主が任意で買い取ることができます。あくまでも任意であるため、事業主と労働者の間で合意が必要となります。
もし、買い取ることとした場合、労働者によって異ならないように、統一的な取扱いをすることが大切です。
急な退職で、労働者が残りの年次有給休暇を取得することにより、後任者などへの十分な引継ぎが行えず、業務に支障が生じるときは、労働者の意思を尊重しつつ、話し合いにより退職日の調整または年次有給休暇の買い取りを検討しましょう。
年次有給休暇の義務化
年次有給休暇の義務化とは?
労働基準法の改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、事業主は、年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。
この義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科されることがあります。
この義務化に対応するため、労働者が、年10日以上の年次有給休暇があるが、既に請求や取得している年次有給休暇が5日に満たない場合、事業主は、その労働者に対し、時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
そのため、就業規則を作成している事業者は、取得義務に関する規定が記載されていなければいけません。
時季指定と計画年休の違いと活用
時季指定は、事業者が労働者の意向を踏まえつつ、年次有給休暇の取得日を指定する方法です。
一方、計画年休は、労使協定に基づき、事前に年次有給休暇の取得日を計画的に割り振る制度です。
これらの制度を適切に活用することで、業務への影響を最小限に抑えつつ、年次有給休暇の取得を促進できます。
まとめ
就業規則における年次有給休暇の規定は、企業のコンプライアンス遵守だけでなく、従業員のワークライフバランスを改善するだけでなく、優秀な人材の確保や定着にも繋がります。
就業規則を自分で作成したけど、その就業規則が法令に違反していないかや労務上問題がないかなど、専門家に一度見て欲しいなどご要望がありましたら、ご連絡ください。